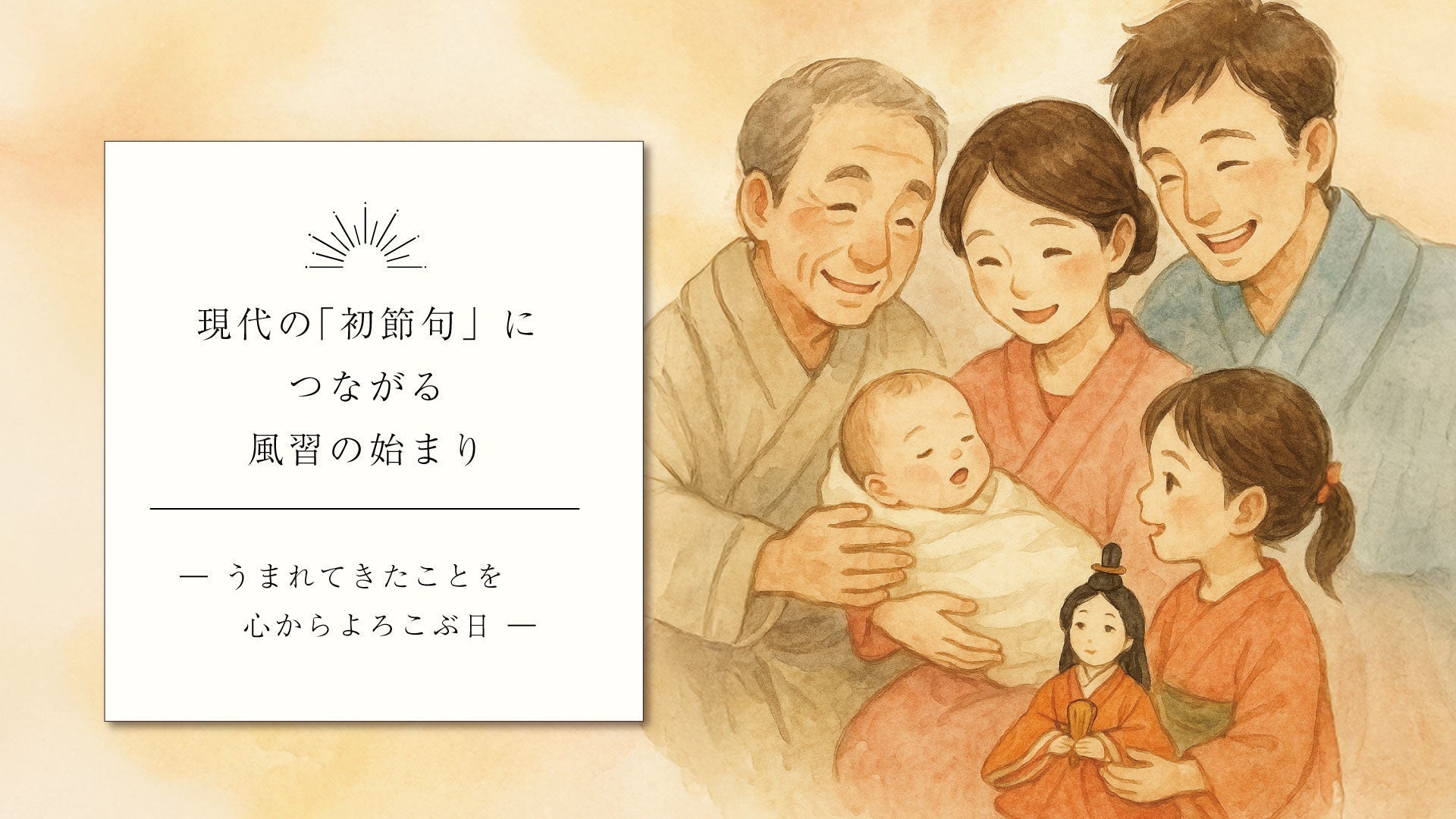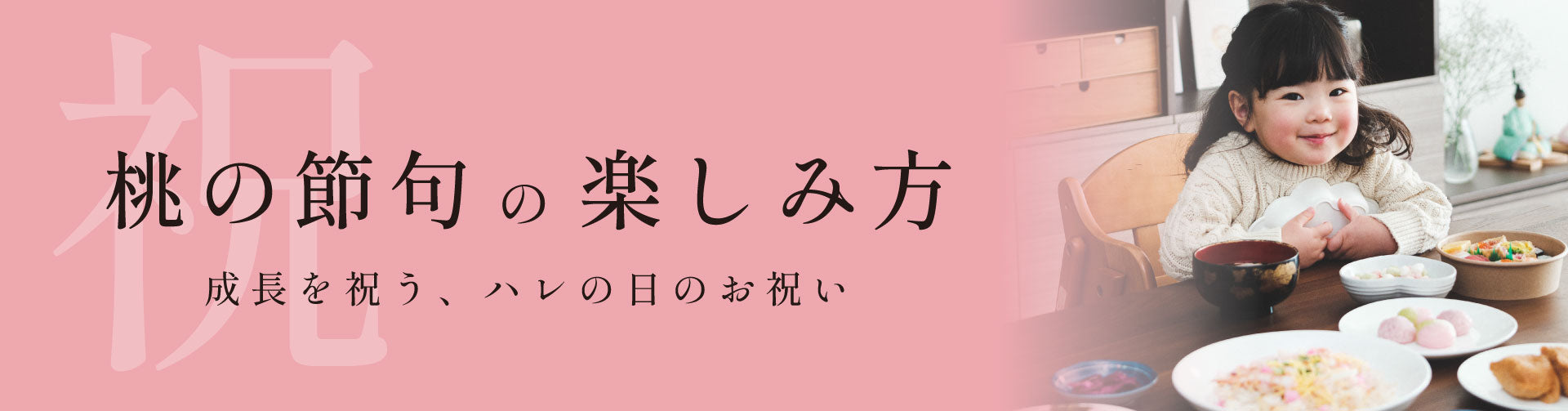雛人形のはじまりには、平安時代の貴族の子女たちがたしなんだ「ひいな遊び」という、ままごとのような人形遊びがあります。
人形に着物を着せたり、身の回りの小さな道具をそろえたり――。それはただの遊びではなく、季節の行事や暮らしのしつけ、教養の一部として、大切に受け継がれてきたものです。
また、「貝合わせ」や「双六(すごろく)」など、当時の女の子たちが楽しんださまざまな遊びも、現代のひなまつりに通じる、和の感性とつながっています。
本記事では、雛人形にまつわる優雅な和の遊びを通じて、ひなまつりの背景にある、平安の雅な世界をひもといていきます。
■ ひいな遊び(雛遊び)

紙や土で作られた小さな人形を使って、おままごとのように遊びを楽しみます。
人形に衣裳を着せたり、家財道具を並べたり、まるで現代のドールハウスのような精巧さも。 遊びながら
生活の知恵や礼儀作法を学び、女の子たちの大切な教養の一つでした。

■貝合わせ(かいあわせ)

対になる貝殻を探して合わせ、記憶力と感性を楽しむ。
ハマグリの内側に美しい絵や和絵、ぴったり合う貝殻を探して遊びます。 ハマグリ
の貝殻は、同じ貝以外とは一時的に合わせない遊びなので、「一生に一人の伴奏」の象徴ともされ、婚礼道具や雛道具にもなりました。
■ 投扇興(とうせんきょう)

扇子を投げて早速、優雅で上品な遊び。
的には「蝶」をかたどった飾りが使われ、風雅な得点表によって競います。
雛人形の飾りにも、扇やが使われることが多く、共通する蝶美意識を感じる遊びです。

■ かるた(歌かるた)

和歌やことば笑って遊んで、日本古来のカードゲーム。
百人一首のような古典文学に優しいことを目的とした「教養かるた」や、言葉遊びとして楽しむ「絵かるた」など、いろんななかたちがありました。
ひな祭りの季節には、家族でかるたを囲む光景も大切にされてきました。
■お手玉・おはじき・折り紙など(江戸〜明治時代以降)

時代が下ると、お手玉やおはじき、紙といった素朴な遊びも女の子たちに広まりました。
色や形、手の動きの美しさなど、日本の美意識が詰まったあそびばかり。これらは
昭和の時代まで長く親しまれ、今もひなまつりイベントなどで再現されることもあります。
■雛祭りの遊びは、「願い」を伝える時間
「和の遊び」は、ただ楽しむだけでなく、遊びの中にこめられた教えや思いを、自然と子どもたちに伝える役割も待ちきました。 雛人形を飾ることも、遊ぶことも、そこには「元気に育ってほしい」「幸せな人生を待ってほしい」という家族のまなざしがあります。