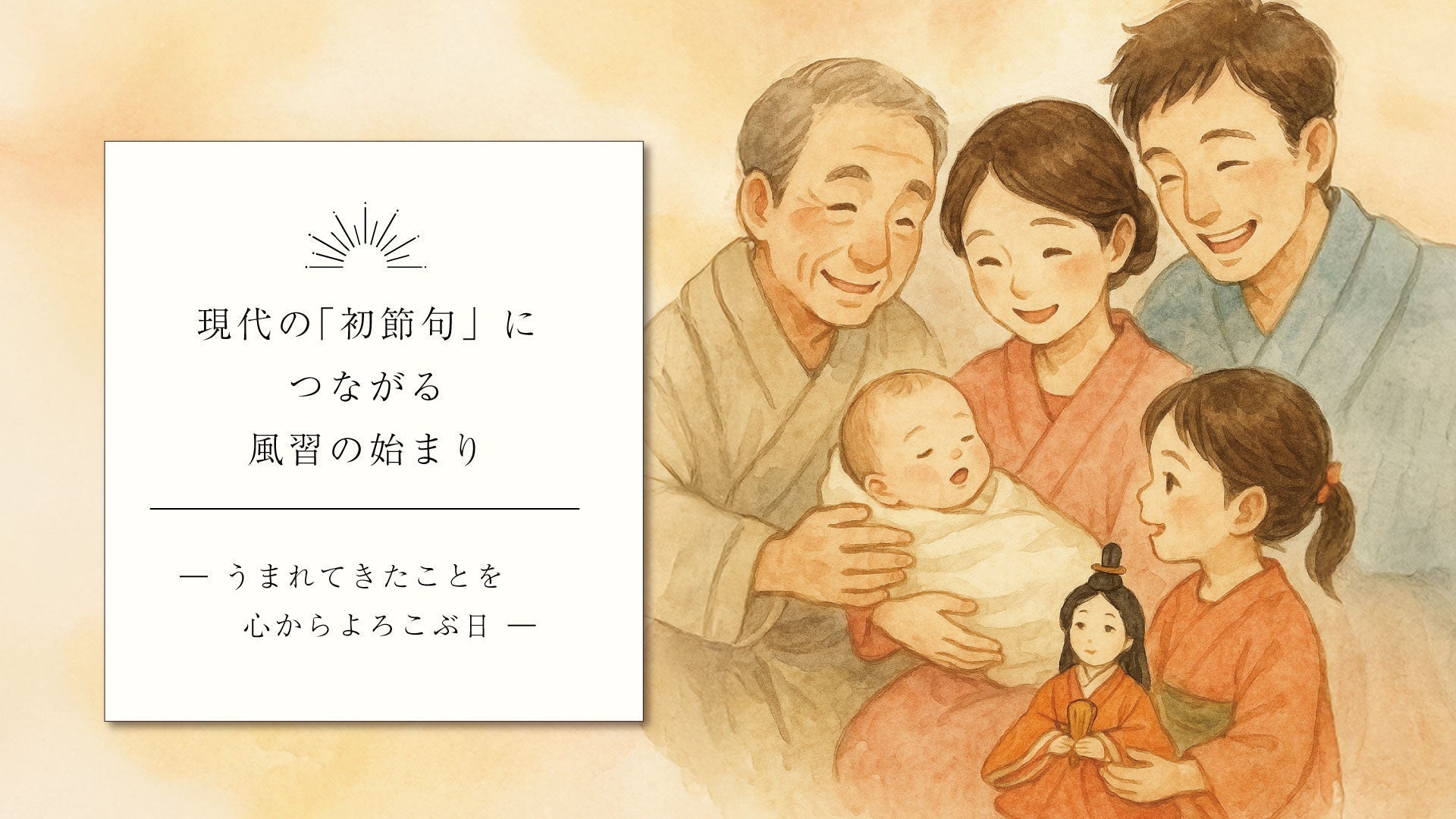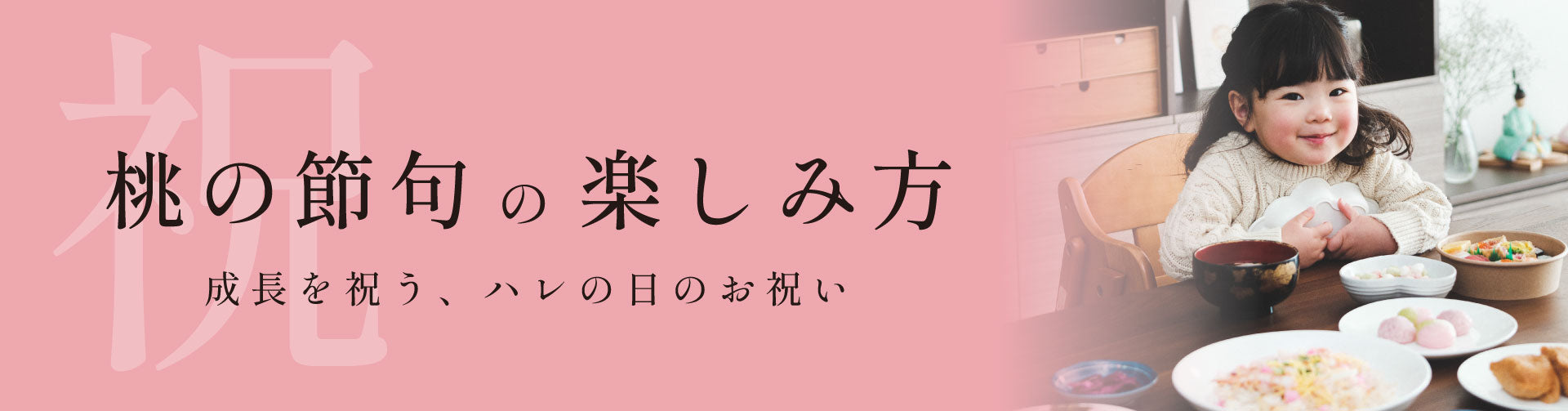古代中国の暦や風習が日本に伝わり、「五節句」として定着していく中、3月3日は「上巳(じょうし/じょうみ)の節句」と呼ばれていました。
「上巳」とは、本来は 3月最初の巳(み)の日のこと。のちに日付が固定されて、現在の「3月3日」になりました。
この日には、春の訪れとともに身体に悪いもの(邪気)が入りやすい時期とされており、川で身を清めたり、人形(ひとがた)に自分の穢れを移して流す「禊(みそぎ)」の行事が行われていました。
こうした風習が、やがて日本で独自のかたちへと育まれ、「流し雛」や「ひいな遊び」といった文化を通じて発展していきます。

■桃の節句と呼ばれるようになったわけ
では、なぜ「上巳の節句」が「桃の節句」と呼ばれるようになったのでしょうか。
それは、この時期がちょうど桃の花が咲く季節であり、
また桃の花そのものにも 邪気を払う神聖な力があると信じられていたからです。
中国の古代神話や陰陽五行思想においても、桃は長寿や魔除けの象徴として登場します。
日本でも同じように、桃の花は 春の幸福を運ぶ花、災いを払う花として親しまれてきました。
こうした背景から、やがて「上巳の節句」は、桃の節句という親しみやすい呼び名で広まり、現在に受け継がれるようになったのです。

■呼び名の変化がうつす、文化の重なり
「上巳の節句」から「桃の節句」へという名の変化は、
日本の季節感や自然観が、中国由来の年中行事に重なり合っていたことを示しています。
災害だけを恐れるための行事ではなく、春の訪れや女の子の健やかな成長を喜び、願うという、やわらかく温かなお祭り、形も意味も変わっていたのです。