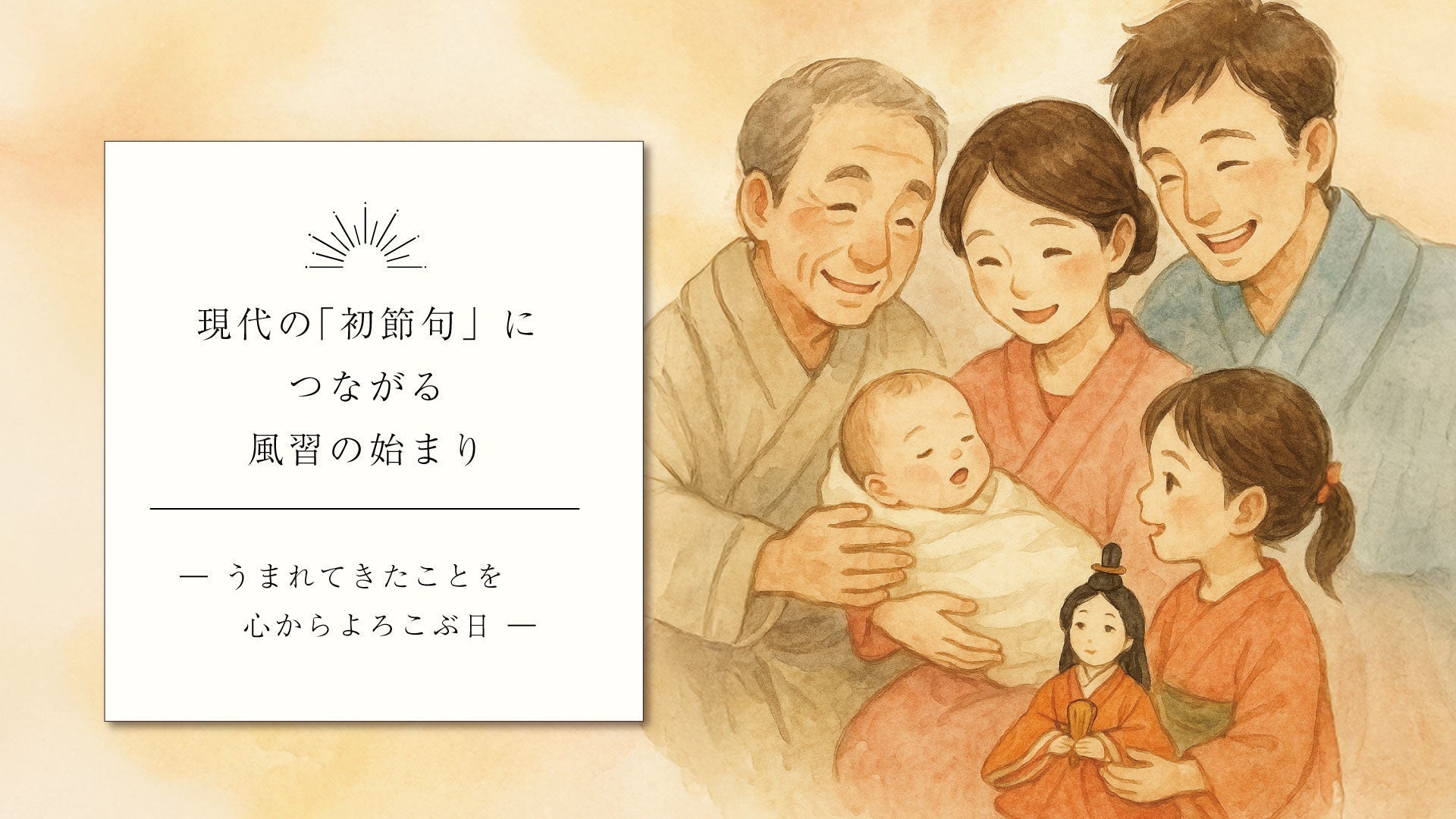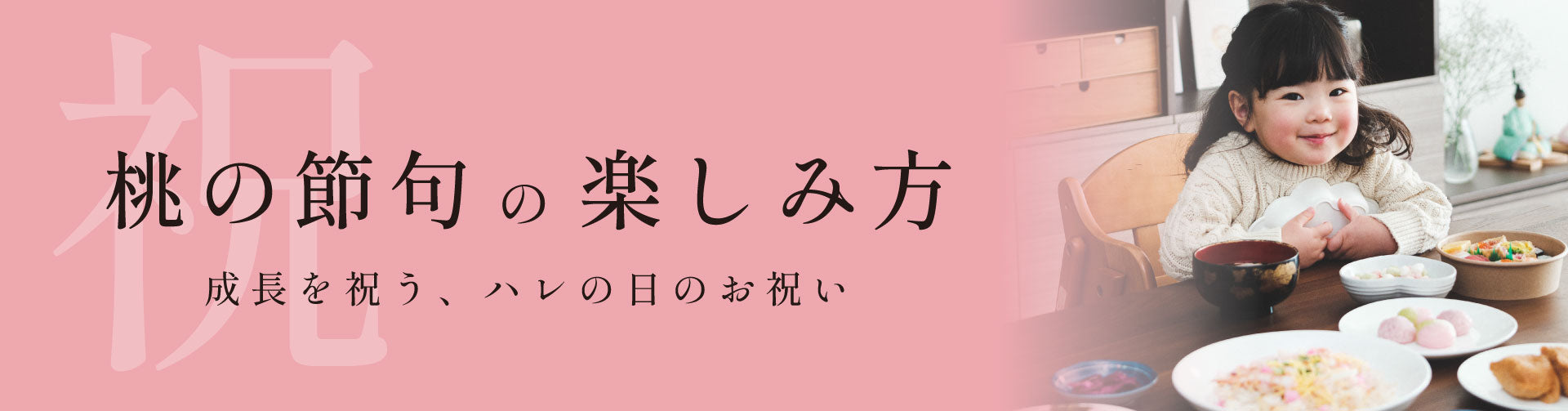初節句とは、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句のことを指し、男の子は5月5日の「端午の節句...
お節句のお祝いをいただいたら
― お返し・内祝いに込めたい気づかい ―
お子さまの初節句...
― 春の訪れと、健やかな願い ―
春の節句として知られる「桃の節句」は、ただ華やかにお祝いする...
私たちが「初節句」としてお祝いしている桃の節句。その原点をたどると、日本古来の「邪気を祓う...
華やかに彩られた段飾り、女の子の健やかな成長を願うあたたかな祝い膳――今の私たちが親しんでい...
桃の節句といえば、きれいに並べられた「段飾りの雛人形」。お内裏様をはじめ、お姫様や三人官女...
桃の節句にまつわる風習のひとつに、「流し雛(ながしびな)」と呼ばれる伝統行事があります。 ...
雛人形のはじまりには、平安時代の貴族の子女たちがたしなんだ「ひいな遊び」という、ままごとの...
ひなまつりのルーツをたどっていくと、平安時代に行われていた「ひいな遊び(ひいなあそび)」と...
春のはじまりを感じる3月。この時期に行われる「桃の節句」は、女の子の健やかな成長を願う、大...
私たちの暮らしの中には、季節ごとに訪れる「節句(せっく)」と呼ばれる伝統行事がありま...