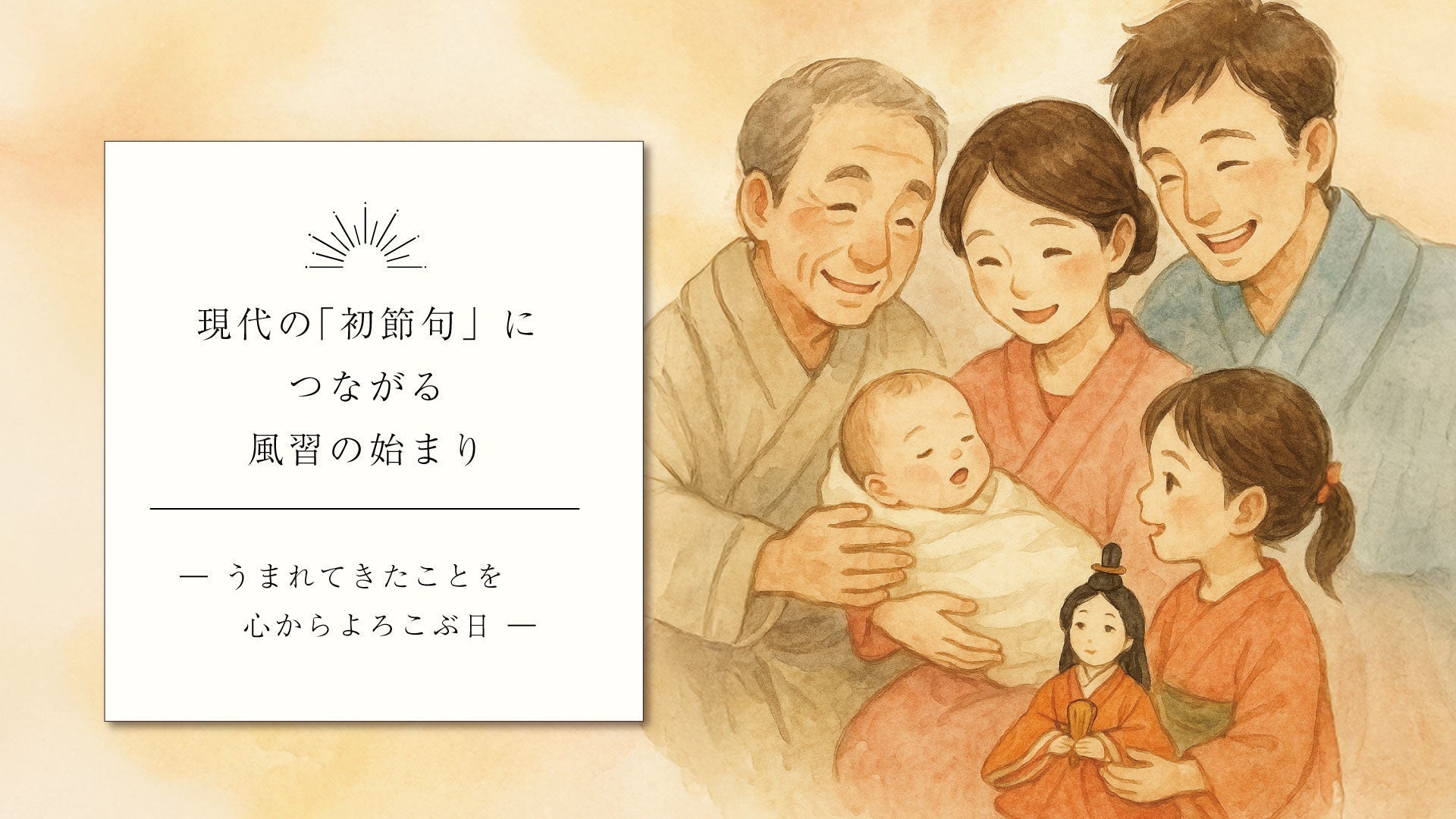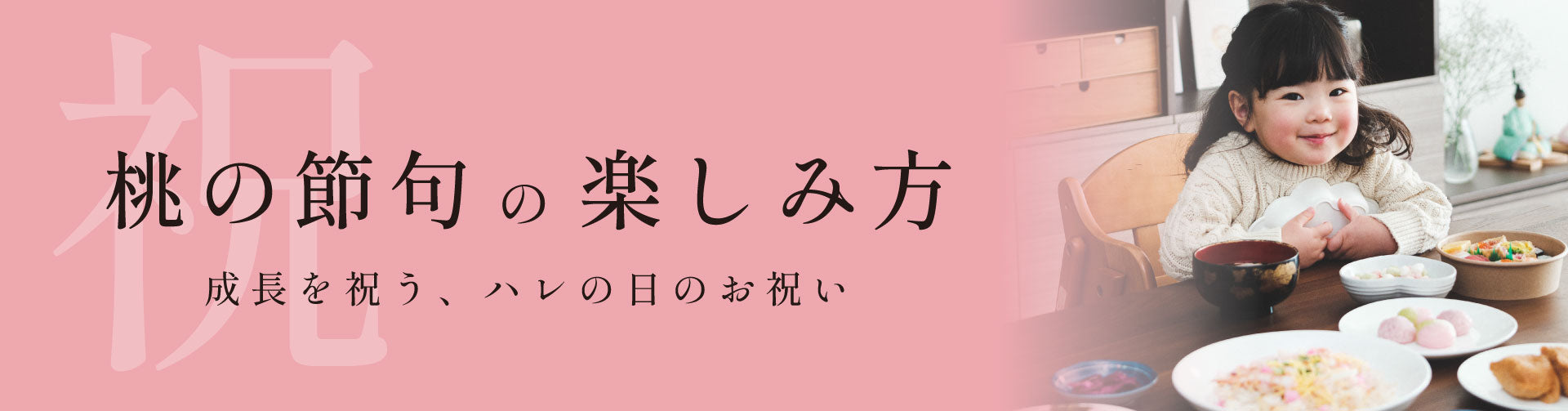― 男雛と女雛、「左右」のちがいにこめられた意味 ―
雛人形を飾るとき、多くの人が「男雛は向かって右?左?」と迷うのではないでしょうか。
実はこの並び方、時代や文化によって異なるのです。
なぜ今の並び方になったのか。その理由をたどってみましょう。

■昔の「左」と「右」は、今の左右とちょっと違う?
押さえておきたいのは、「左=上位、右=下位」という古来の考え方です。
これは中国の儒教の影響を受けた考え方で、日本でも平安時代の宮中は、左大臣が右大臣よりも上というように、「左」が上位とされていました。
このときの左右とは、「自分から見る」ではなく、「正面から見る(=下から見る)」の左右です。
つまり――
●上位=向かって右(男雛)
●下位=向かって左(女雛)
この伝統にのっとって、昔の雛人形は、男雛が向かって右、女雛が向かって左に飾られていました。
今でも京都などでは、この並びが主流です。
その中で、西洋式の「自分から見て左=上位」という左右の感覚が、公の場にも受け入れられるようになりました。
かつて、大正天皇の即位式では――
●天皇(男性)が向かって左
●皇後(女性)が向かって右
に並ぶという、西洋式の配置が採用されたのです。
この影響を受けて、昭和以降の関東圏では、男雛が向かって左、女雛が向かって右に並ぶのが主流になっていきました。
■現代の「左上・右下」の並びは、こうして決めた
現在、デパートやカタログでよくある雛人形は、
●向かって左に男雛(お内裏様)
●向かって右に女雛(お雛様)という
「西洋風スタイル」です。
この並びは、特に関東では北に広く浸透しており、全国的に主流となっているのは、昭和の後半
続き。
■京都や伝統工房では、今も「向かって右に男雛」
堂々、京都や伝統を重んじる地域・工房では、今も昔ながらの「男雛が向かって右」「女雛が向かって左」の並びを守っています
。
「どちらが正しい」というわけではなく、時代や文化の流れの中で、二つの様式が今も共存しているのです。
■並び方に込められるのは、「調和と願い」
男雛と女雛の並び方は、によって変わってきたもの
。
それは――
二人が並ぶことで、調和が生まれ、未来への願いが形になるということ。
ひな人形の左右を範囲歴史を知ると、飾るときの気持ちも、少しだけ深くなるかも知れません。