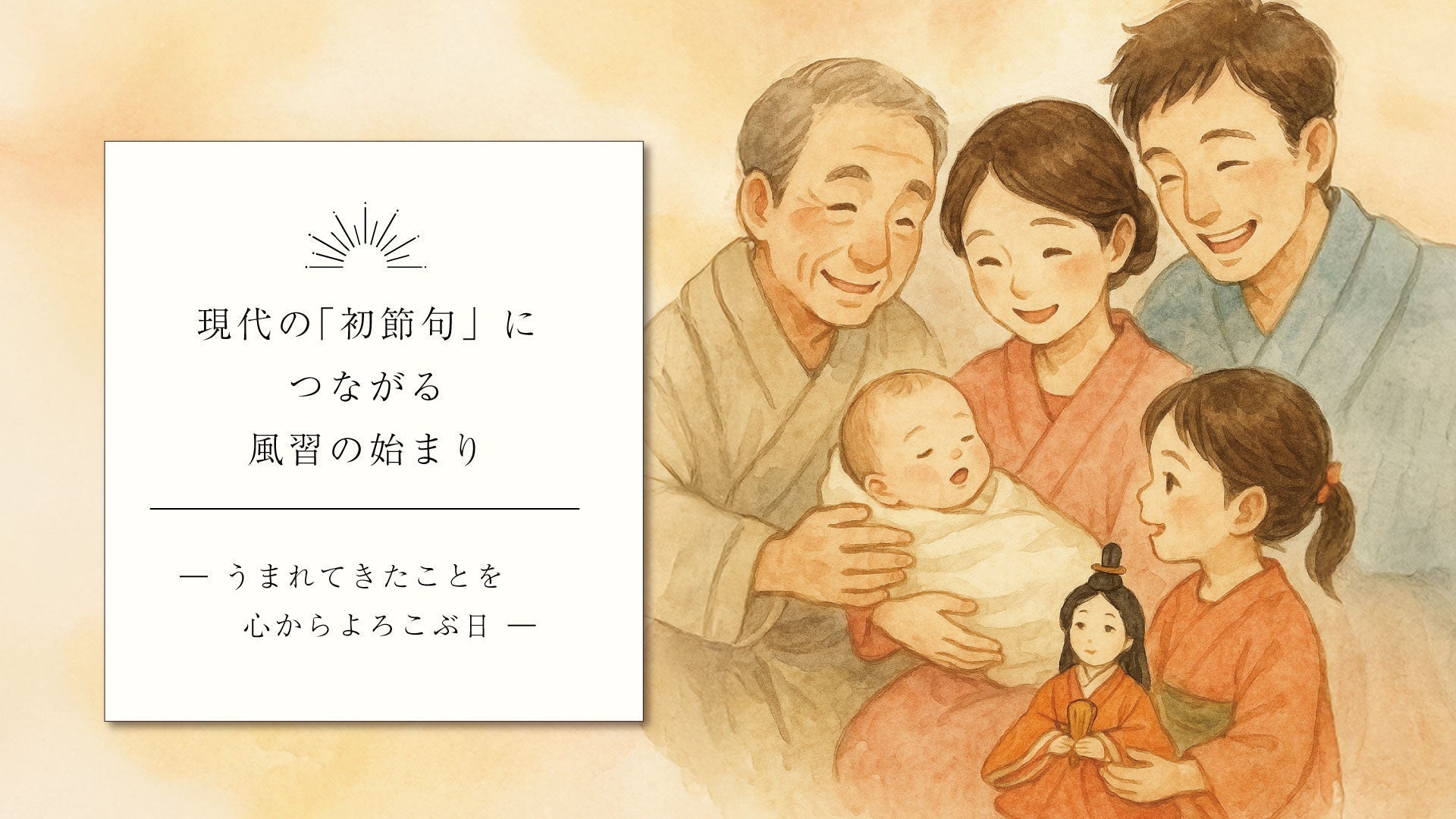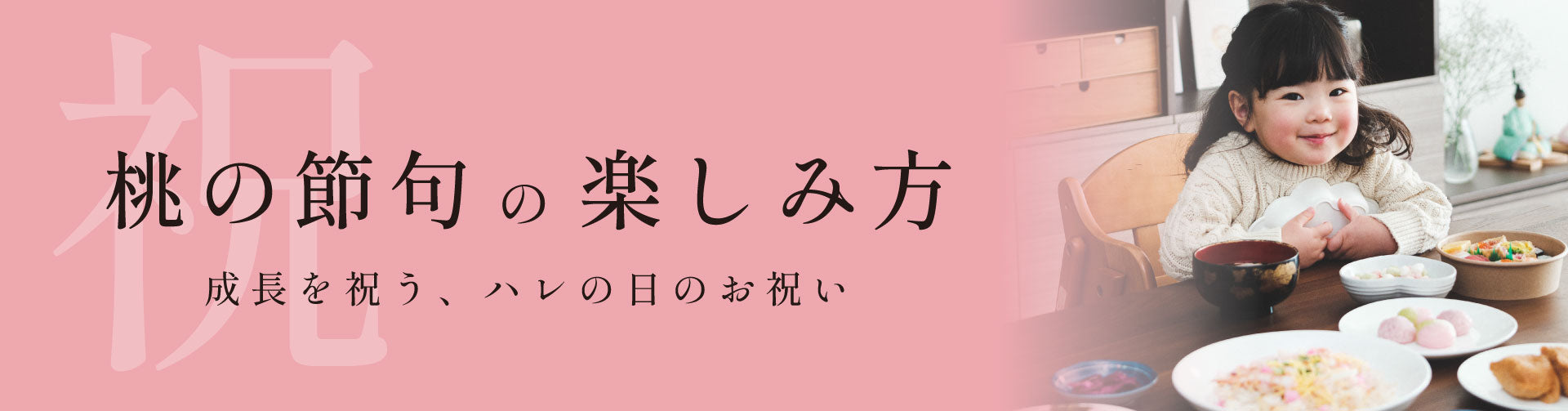ひなまつりのルーツをたどっていくと、平安時代に行われていた「ひいな遊び(ひいなあそび)」という、可愛らしい遊びにたどり着きます。
この「ひいな」は、現在の「雛(ひな)」と同じ意味をもち、「小さくて、かわいらしいもの」を表す言葉でした。
■ 上流階級の女の子たちの、ままごと遊び
平安時代の貴族社会では、紙や土でつくられた小さな人形を使って、女の子たちがままごとのような遊びを楽しんでいました。
これが「ひいな遊び」です。
人形だけでなく、衣裳や道具、お家のような小物も工夫され、当時の暮らしや宮中の様子をうつしたような精巧なものもあったそうです。
日記や物語の中にも、女の子たちが人形で遊ぶ様子がいくつも登場します。

この「ひいな遊び」は、ただの遊びではなく、暮らしの中で自然と育まれてきた「しつけ」や「教養」の一部でもありました。
また、同じように上流階級の子どもたちの間では、「貝合わせ」や「かるた」なども一緒に親しまれていました。
たとえば「貝合わせ」は、美しい貝殻の内側に絵を描き、対になる貝を探して合わせる遊び。優雅な絵柄や和歌が用いられ、遊びながら感性や教養を養う文化的な要素が込められていました。
こうした雅な遊びの数々が、のちに「ひなまつり」と結びつき、女の子の健やかな成長を願う行事へと育まれていくのです。
■ 遊びから、祈りのカタチへ
やがてこの「ひいな遊び」と、3月3日の「上巳の節句」に行われていた厄払いの風習が結びつき、
人形を飾って願いを込める、今のひなまつりの原型が生まれていきます。
つまり、現代の「ひな人形を飾ってお祝いする文化」は、遊びと祈りが合わさってできた、あたたかな風習なのです。

■ 現代に受け継がれる「ひいな」のこころ
今でも、お子さまたちがお雛様の前でごっこ遊びをする姿を見かけることがあります。
それは、まさに「ひいな遊び」の名残といえるかもしれません。
遊びの中に、家族の願いや暮らしの知恵がそっと息づく――
そんな平安の女の子たちの姿を思い浮かべながら、ひなまつりを迎えるのも素敵ですね。