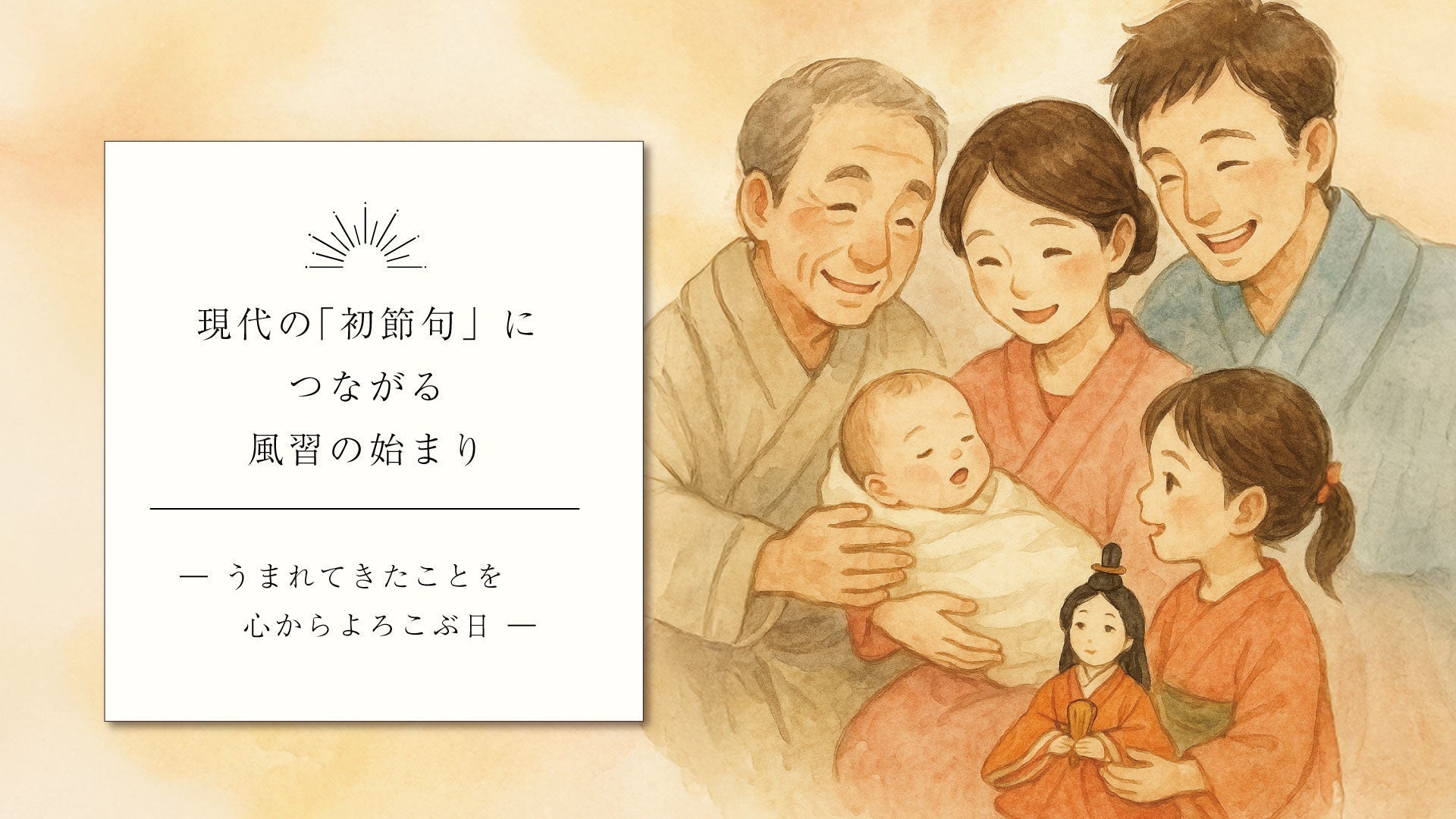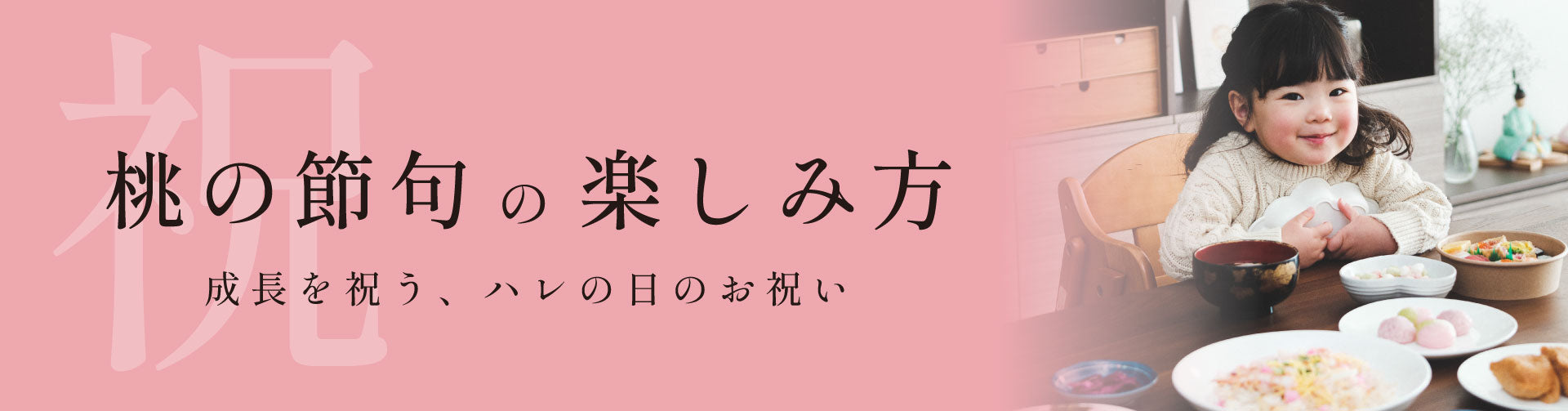― 春の訪れと、健やかな願い ―
春の節句として知られる「桃の節句」は、ただ華やかにお祝いする日、というだけではありません。その始まりには、「邪気を祓い、大切な命を守る」という、深い祈りの心が込められています。
1. 春は「災いの季節」だった
今の私たちにとって春は、穏やかな季節
。
気温の変化があり、疫病が流行しやすい。
田畑の仕事が始まる前の不安定な季節。
特に3月の初めは「邪気が入りやすい時期」とされ、人々は不安とともに過ごしていたのである。
この「春の不安定さ」こそが、のちの「上巳の節句」や「桃の節句」の成立に深くかかわります。

2. 上巳の節句と「形代(かたしろ)」の考え方
古代中国では、3月の初旬(上巳)に「水辺で身体を清め、災いを祓う」風習がありました。これが
日本に伝わると、人の形をした「形代(かたしろ)」に自分の穢れや厄を移し、それを川に流す「流し雛」の形に。
この「身代わりに災厄を受けてもらう」という考え方は、日本の古代信仰にもあります。 たとえば
、『万葉集』や『延喜式』にも記される「人形(ひとがた)」の場面
。
ここに、「ひなまつり=邪気祓いの祭り」の本質が見えてきます。

3. 「桃」の意味 ― 命を守る力ある木
さらに、桃の節句における「桃の花」にも、深い祓いの力が込められています。
桃は中国では古来より「仙木(せんぼく)」と呼ばれ、不老長寿・厄除けの象徴。
日本でも、鬼を退治する『桃太郎』や、神話に登場する「桃の実」にその霊力が語られます。
平安時代には、宮中で桃の花を使っていた「桃花酒(とうかしゅ)」を飲んで無病息災を願う風習も。
桃の花はただの春の飾りではなく、春の災厄を遠ざけ、命を守る象徴だったのです。
4. 人形が「飾るもの」へ ― 守りの交渉から文化へ
最初「祓いのための人形」だった雛は、しだいに飾りとしての要素を持ち始めます。 特に
平安時代には、宮中の姫君たちが行っていた「ひいな遊び(おままごと)」の人形文化と緊張感、
人形=守り+遊びの対象、という二面性をもつようになります。
そして江戸時代には、それが段飾りへと発展し、女の子の成長を祝う文化へ。それでもその
根には、「この子の人生が、災いなく健やかでありますように」という祈りが残り続けています。
5. 現代に受け継がれる「祓い」と「願い」
今の私たちは、雛人形を「飾るもの」「贈るもの」としてとらえがちです
。
雛人形を飾るという行為は、たんに伝統を守ることではありません。
お雛様を飾り、桃の花を添え、家族みんなでお祝いの席を囲む。その
ひとつの行動が、時をこえて受け継がれてきた「日本のこころ」の一つかもしれません。