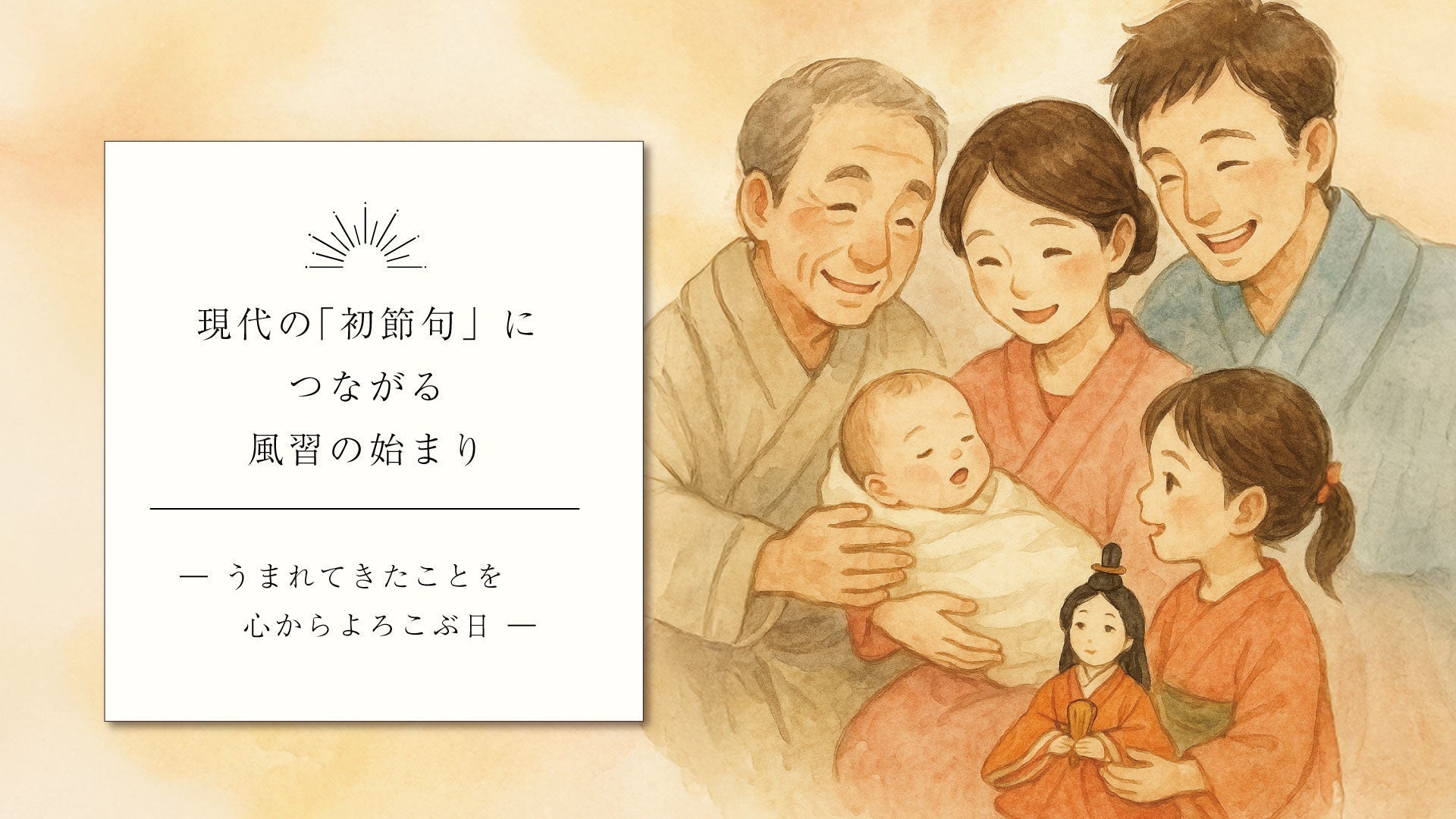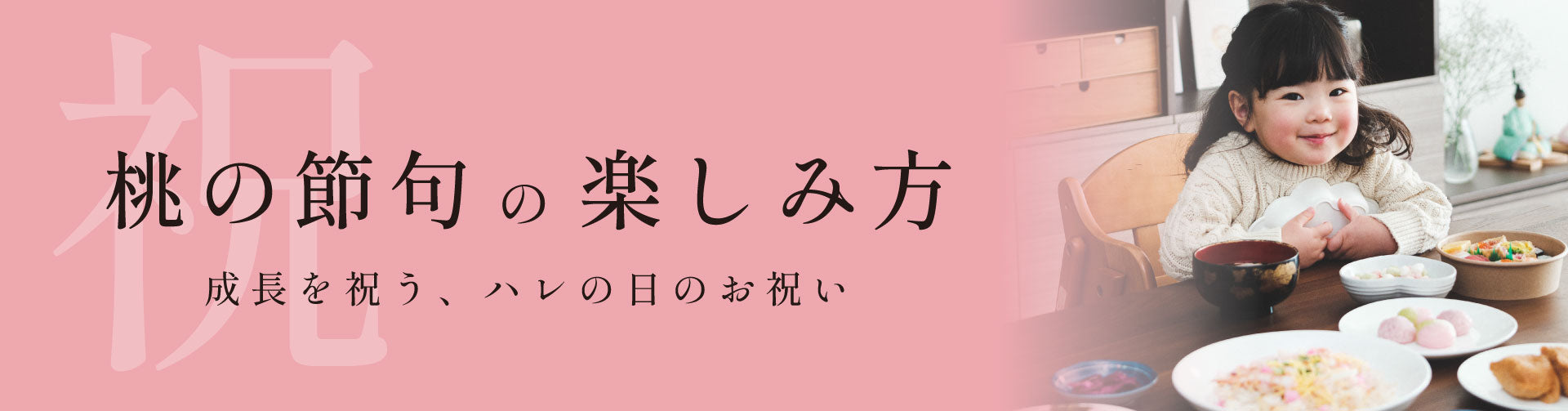華やかに彩られた段飾り、女の子の健やかな成長を願うあたたかな祝い膳――
今の私たちが親しんでいる「雛祭り」の風景が、かたちとして整い、暮らしの中に広がっていったのは、まさに江戸時代のことでした。
それまで、貴族や武家のあいだで静かに伝えられてきた雛人形の文化が、江戸の町人文化とともに、庶民の年中行事として花ひらいていったのです。
■ 江戸幕府が定めた「五節句」のひとつに

江戸時代のはじまり、幕府は一年の節目となる重要な日を「五節句」として正式に定めました。
そのひとつが、3月3日の「上巳(じょうし/じょうみ)の節句」。
この日を、女の子の厄除けと健康を願う行事として、雛人形を飾る風習が盛んになっていきます。
もともとは宮中行事や上流階級のならわしだった雛祭り。
それが“幕府公認の年中行事”となったことで、庶民の暮らしにもゆるやかに広がっていったのです。

■ 大奥や武家でも雛人形が愛された
雛祭りは、とくに武家の女性たちに大切にされました。
将軍の住まう江戸城の「大奥」では、女の子の無病息災を願い、美しく贅沢な雛飾りが並べられていたといいます。
また、大名家の嫁入り道具のひとつとしても雛人形は重宝され、「家の格式」をあらわす存在でもありました。
大切に保管され、代々受け継がれていく雛人形は、家をつなぐ“宝物”のような存在でもあったのです。

■ 町人文化とともに“飾る楽しみ”が広がる
江戸の町に暮らす庶民たちにとっても、雛祭りは楽しみな年中行事のひとつとなっていきました。
人形づくりの技術が発達し、豪華な雛道具や細工ものが次々と登場。
親たちは、女の子の「初節句」を祝うために、一生に一度の雛人形を用意しようと工夫を重ねました。
また、「節句見世(せっくみせ)」と呼ばれる、豪華な雛飾りを店先に飾る風習も江戸の町に広がります。
これは一種の“お披露目”でもあり、道ゆく人々が足をとめてその美しさを楽しむ、暮らしの中の春の風物詩でした。

■ 女の子のための“はじめての祝い”として
この頃には「初節句(はつぜっく)」――女の子が初めて迎える3月3日を、家族みんなでお祝いするというかたちも定着していきます。
お膳をととのえ、着物を着せ、雛人形を飾り、親戚やご近所にもお披露目する。
そこには、「無事に生まれてきてくれてありがとう」「これからも元気に育ってね」という、まっすぐな愛情と祈りが込められていました。
江戸の人々にとって、雛祭りは単なる行事ではなく、女の子のいのちと人生を、家族であたたかく見守る節目だったのです。

■ 雛祭りが“文化”として根づいた時代
こうして江戸時代を通じて、雛人形はより豪華に、より精緻に、より多様に進化していきます。
お人形の表情や衣装、道具の細工には、職人の技と美意識が込められ、江戸中期にはついに「段飾り」というかたちが登場しました。
季節を味わい、願いをかたちにし、美しさをくらしの中で楽しむ。
江戸時代は、まさに雛祭りが行事から文化へと育っていった時代だったといえるでしょう。