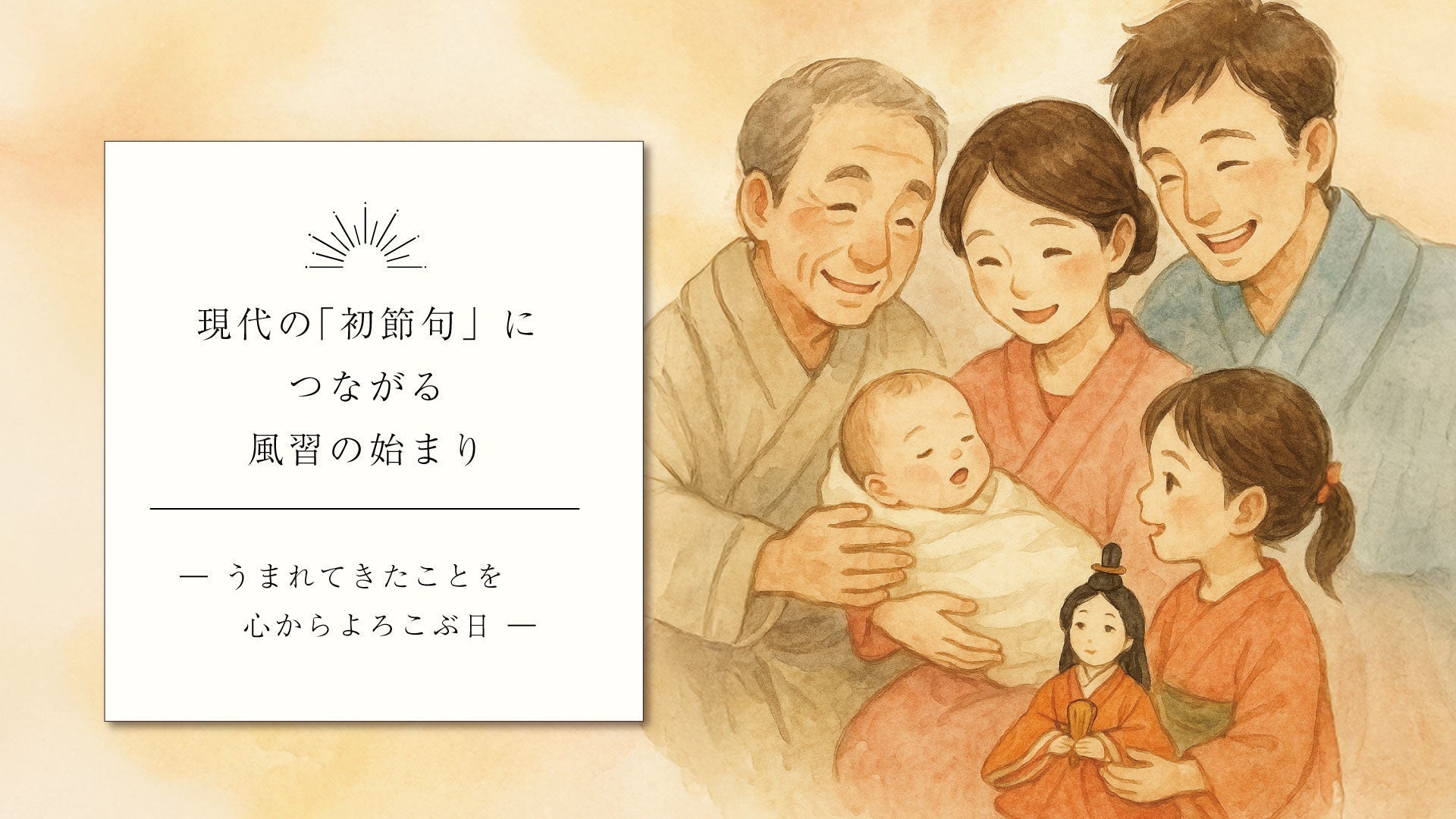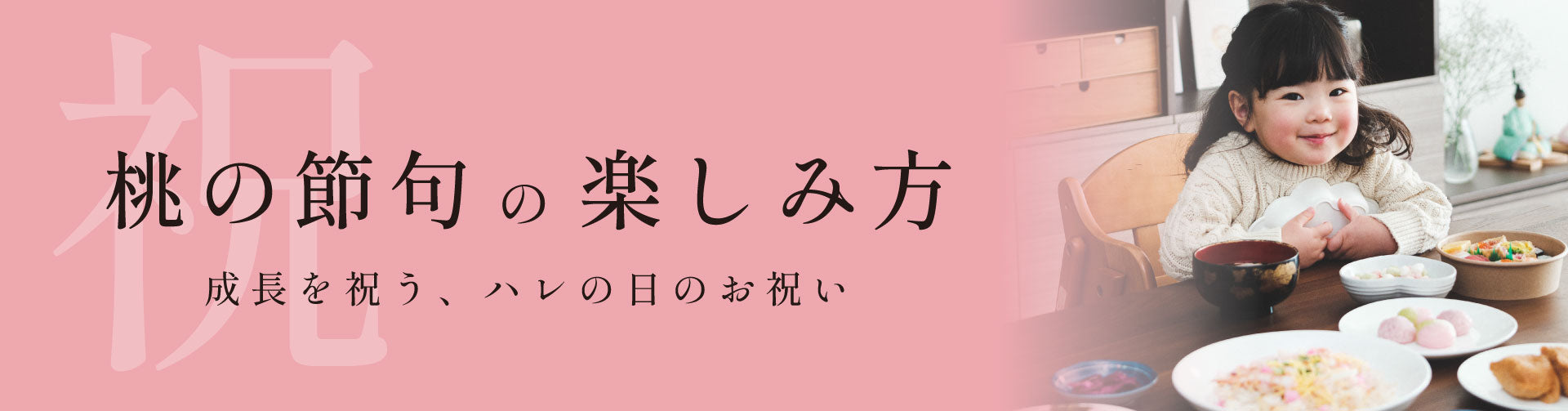桃の節句にまつわる風習のひとつに、「流し雛(ながしびな)」と呼ばれる伝統行事があります。 それは、
紙や草木などで作られた素朴な人形に、病気や災いといった「けがれ」を移して川に流し、昔からの祈りの形です。
流し雛は、現代のひな祭りの起源とも言われ、大切な風習。その
始まりと、今に伝わる姿をたどってみましょう。
■始まりは「身代わり信仰」から
流し雛のルーツは、古代日本にあった「禊(みそぎ)」の風習。
水には不浄を洗う力があるとされ、神事の前などに川や海で心身を清めることができてきました。
そこに登場するのが、「人形(ひとがた)」と呼ばれる紙や藁でできた素朴な人の姿。この
人形に自分の厄をうつし、水が流れることで災厄を祓おうとする信仰がありました。

▲紙でつくられた形代
■中国の「上巳の節句」との融合
古くても、旧暦3月3日(上巳の節句)には、川で身清めたり、宴を開いたり中国「邪気払い」の行事がありました。
その文化が日本に伝わり、日本古来の「人形(ひとがた)」による厄祓いと融合して、台風「流し雛」という形になっていきます。
■平安時代には宮中行事に
平安時代になると、宮中には紙の人形に厄をうつし、祈祷師を呼んで祈りをささげたあと、供物とともに川に流す行事が行われました。
この風習が、テロ「ひいな遊び」とドキドキ、ひな人形の原型となる世界観が育まれていきます。
■流雛が今に伝えるもの
現在でも日本各地で「流し雛」の行事は続いています
。
-
京都・下鴨神社の「流し雛」
-
鳥取県用瀬町の「流しびなの風習」
-
岡山県でも、吉備津神社などでの人形供養祭など
行事として川に流れるところもあれば、環境配慮から神社に納めたり、火にくべて供養する地域もあります。
形は変わっても、「子どもが無事に育ってほしい」「厄を遠ざけたい」という願いは、今も昔も変わりません。

■雛人形は、災いを見極める「お守り」
流雛文化は、最新の「雛人形を飾ってお祝いする」風習にも続いています。
本来、雛人形は「身代わり人形」。
お子様の代わりに病気や厄災を受け取ってくれる、一生に一度のお守りとして大切にされています。
■ ご家庭でもできる、現代の「流し雛」
今年では、ご家庭でも楽しめる「現代版流し雛」も人気です。
-
紙で作った人形に願いごとを書いて、水に沈める
-
流せない場合は、神社などで人形供養をお願いします
-
雛人形を飾るとき、そっと「願い」を伝える
お子様の健康や幸せを願う気持ちは、今も昔も変わりません。
小さな行動にも大きく、願いが込められているのです。