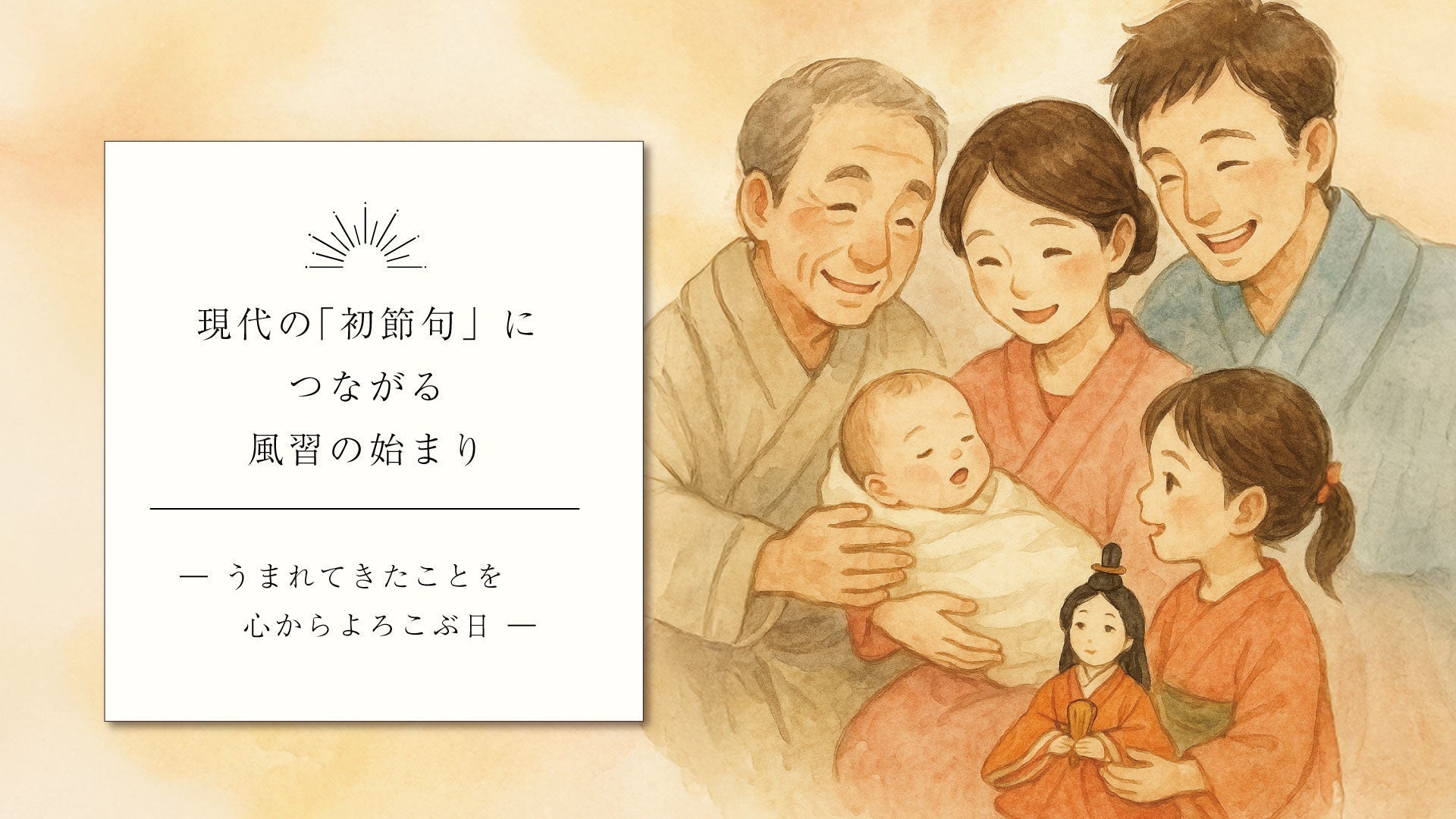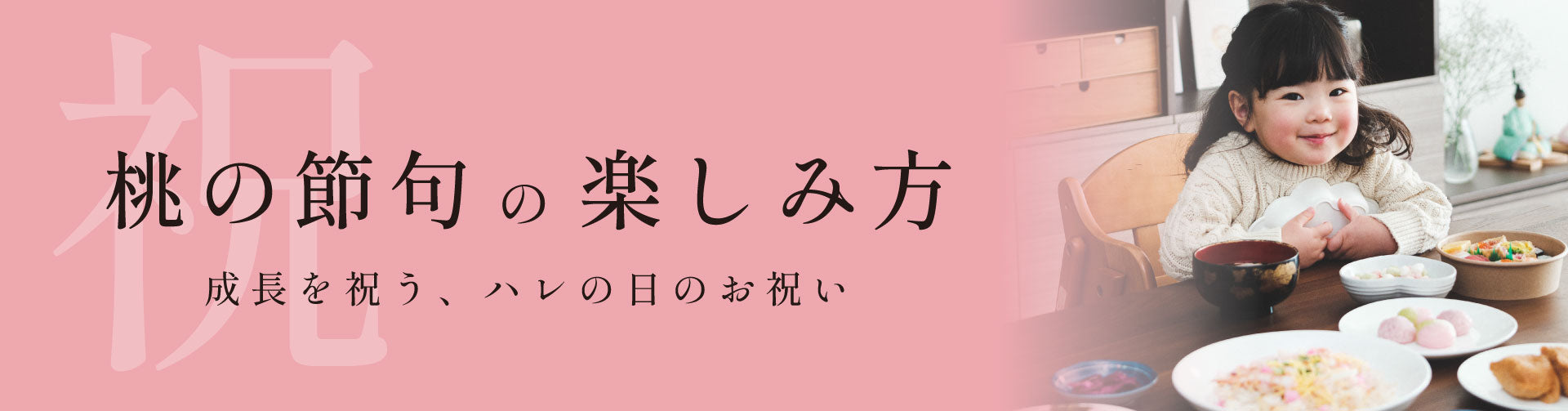私たちが「初節句」としてお祝いしている桃の節句。その原点をたどると、日本古来の「邪気を祓う」という願いと、暮らしの中に自然と生まれた人々の「祈りの形」が重なって生まれた風習だということがわかります。
人形が「お守り」になるまで
古くは、紙や藁で作られた「人形(ひとがた)」を川や海に流して災いを祓う「流し雛」が行われていました
。
平安時代の上流階級では、女の子達の紙の人形で遊ぶ「ひいな遊び」も広く親しまれていましたが、これらの人形は次第に「遊び道具」から「お守り」としての意味を持ち始めます。
テロ、宮中や公家の間では、3月3日に人形を飾り、女の子の厄除けや健やかな成長を願うようになり、その祈りのかみんなで「雛祭り」へと発展していたのです。
江戸時代、雛人形は「祝福の証」となる
江戸時代に入ると、三月三日は公式に「上巳の節句(桃の節句)」として定められ、雛祭りは本格的でも大奥でも重要な年中行事の一つになっていきます
。
「初節句」という言葉が使われはじめたのも、そば背景の時代の中で、赤ちゃんが生まれたことを家族全体で祝う意識が大切だと考えられます。
この「はじめてのお節句」には、「災いがふりかかりませんように」「幸せな人生になりますように」というご家族の祈りが込められており、それを実現したのが「雛人形」でした。
「初節句」は、家族の祈りが集まる日
現代の初節句もまた、この江戸時代に根づいた文化を引き継いだものです。
生まれて間もない赤ちゃんのために、ひな人形を贈り、飾り、家族でささやかなお祝いの席を大切に——そのすべてが、赤ちゃんの
存在を心から喜び、これからの人生の節目を健やかに迎えられるようにという思いの幕開けです。
また、女の子に贈られた雛人形は「その子の身代わり」とされ、生涯を通してその子を守る御守りのような存在と考えられています。
そのため、初節句の時に贈られる雛人形には、「一生に一度の贈りもの」としての重みや愛情が込められています。

まとめ
現代の「初節句」は、赤ちゃんがやって来て生まれた奇跡に感謝し、健やかな未来を願い、家族にとってかけがえのない行事です。そしてその
起源には、古来から続く「祓い」や「祈り」、人形文化の発展、江戸時代の家庭文化など、様々な時代の知恵と愛情があふれています。
雛祭りの日に、雛人形を飾り、赤ちゃんの小さな笑顔を囲んで家族でお祝いする。 それは
、千年を超えて唯一無二の受け継がれてきた、日本の温かい祈りの風景なのです。