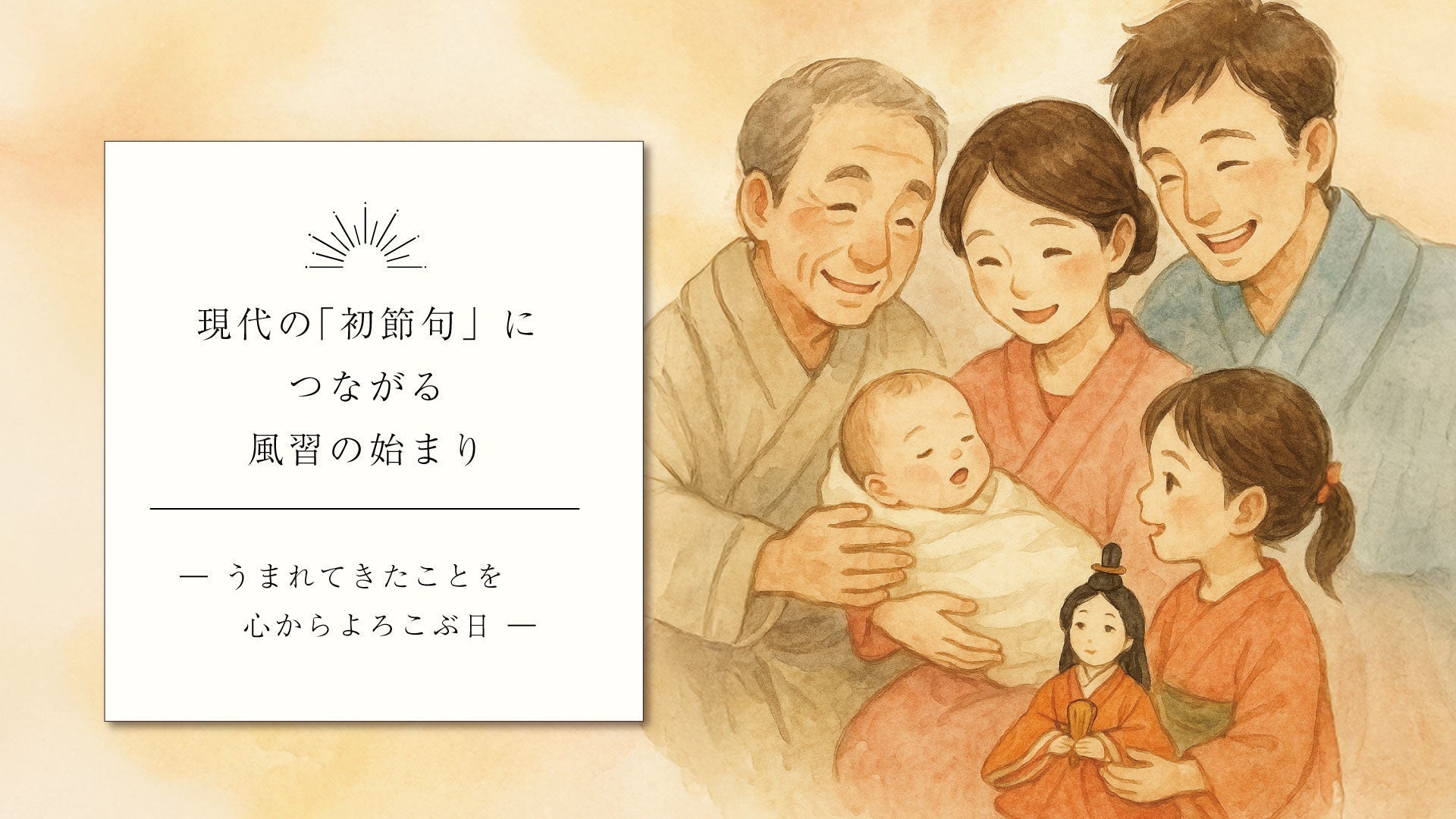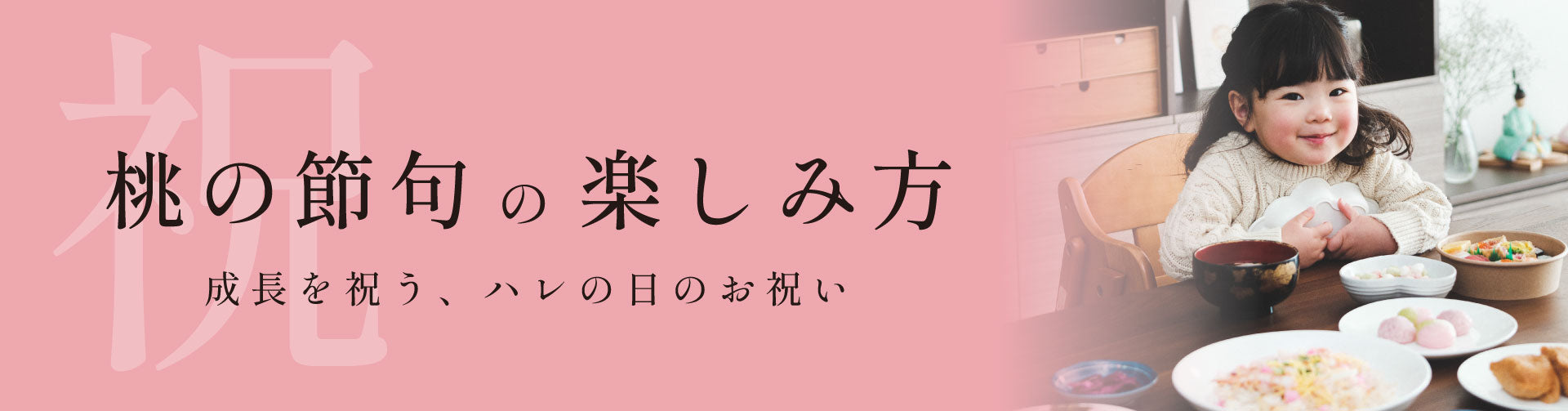春のはじまりを感じる3月。
この時期に行われる「桃の節句」は、女の子の健やかな成長を願う、大切な年中行事です。
では、なぜこの日、「お雛様」を飾ってお祝いするようになったのでしょうか?
■ 古くから続く、季節の節目の「厄払い」
もともと3月3日は、「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれる季節の節目でした。
昔の人々は、季節の変わり目には邪気が入りやすいと考え、災いを払うためにさまざまな工夫をしていました。
そのひとつが、「人形(ひとがた)」に自分のけがれを託し、水に流して清めるという風習。
これが、今の「流し雛(ながしびな)」や「雛人形」の原型になったといわれています。

■ お雛様は、お子さまの『一生に一度の御守り』
やがて、女の子が生まれてはじめて迎える「初節句」に合わせて雛人形を贈る習わしが生まれました。
お子さまに「災いが降りかからないように」という願いと、「幸せな人生を歩んでほしい」という思いを込めて贈られるお雛様。
それは、成長をそばで見守ってくれる、一生に一度の御守りともいえる存在です。
お雛様には、女の子が無事に成長し、自立するまでの人生の節目にそっと寄り添い、厄を引き受けるという役割があります。
■ 今も昔も、家族の想いをカタチにするひなまつり
現代でも、「無事に生まれてきてくれてありがとう」「元気に育ってくれてうれしいね」という気持ちを込めて、お雛様を飾り、お祝いをします。
春のやさしい光の中で、ご家族が心を寄せ合いながらお子さまの幸せを願う――。
そんなあたたかな時間こそが、ひなまつりの本当の意味なのかもしれません。
お雛様は、過去から未来へと続く、ご家族の願いの象徴です。