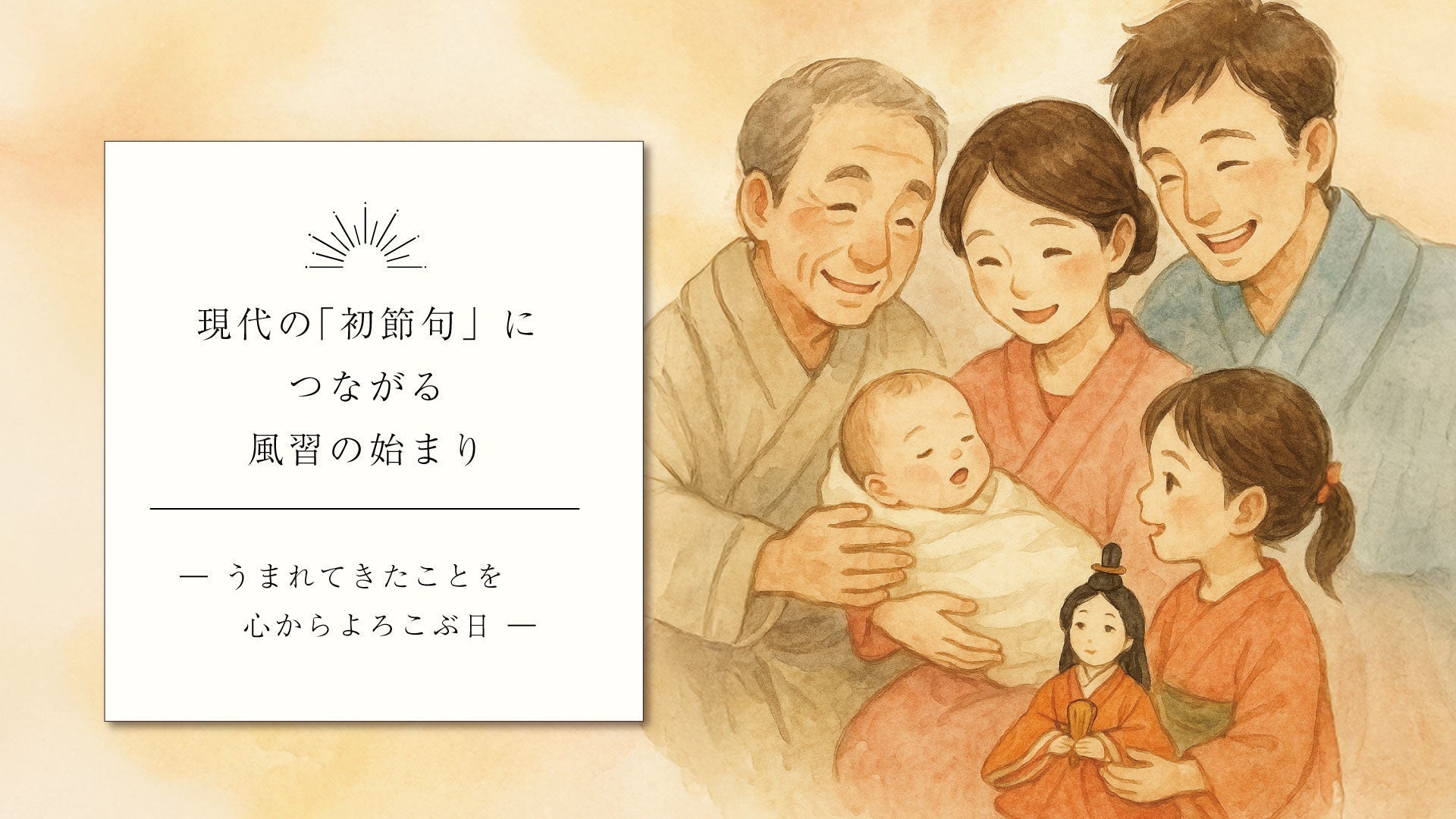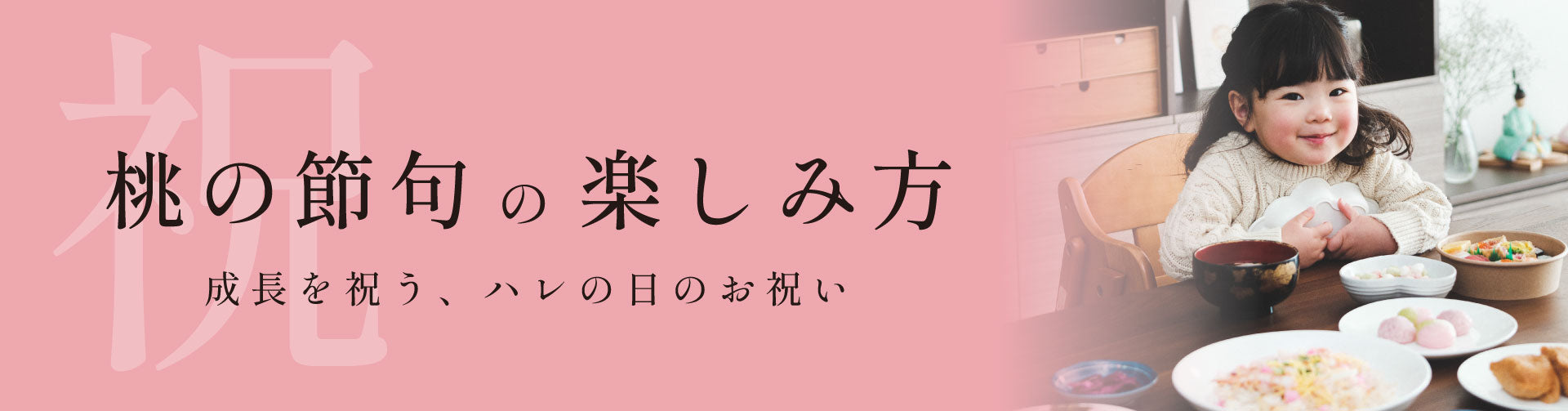桃の節句といえば、きれいに並べられた「段飾りの雛人形」。
お内裏様をはじめ、お姫様や三人官女、五人囃子など、華やかな人形たちが階段状に並ぶ姿は、春の風物の詩ともいえます。
雛人形を飾り始めた当初、雛人形は段飾りではありませんでした。
その背景には、暮らしの変化や人々の想いがありました。
■はじめは「対」の雛人形だった
雛人形がはっきりと記録がある江戸に現れるようになるのは、時代のごろ初めです。
当時は「内裏雛(だいりびな)」と呼ばれる、男雛と女雛の一対だけを飾るのが一般的でした。
これは、天皇と皇后を模したお人形で、「夫婦が仲睦まじく、幸せな人生を歩めますように」と願いが込められていたとされます。

■ 段飾りの誕生は江戸時代中期から
戦略江戸時代も中期になると、雛人形の飾り方に少しずつ変化が現れはじめます。お姫様に仕える「三人官女」や、音楽を奏でる「五人囃子」、お殿様を守る「右大臣・左大臣」など…。
これは単に飾りの拡張ではなく、宮中の世界をぐるっと縮小する「見立て」の文化。
今回の絵巻物や資料には、すでに「段を作って人形を飾る」様子が描かれており、ここから段飾りの原型ができあがっていきました。
■人形が増えすぎて…「段に分けて並べよう」
さて、ここで一つ問題が起きます。
飾りたい人形や道具が増えすぎて、平らな場所だけでは短期間で消えてしまいました。
「これでは見えない、美しくない」
「だったら、階段状にして、上から下まで並べてみよう」
考慮自然に工夫されたのが、最新の「段飾り」のスタイル。
上の段には当然の高い人形を、下の段には家来や道具を並べる。
この配置には、美しさだけでなく、秩序や礼儀を大切にする日本人の価値観が検討されています。
■ 社会の公開?
段飾りの並び順にも意味があります。
段飾りの上から順に、人形の「当然」が高い順に並んでいるのを覚悟でよろしいですか?
-
一段目:内裏雛(男雛・女雛)
-
二段目:三人官女
-
三段目:五人囃子
-
四段目:随身(右大臣・左大臣)
-
五段目:仕丁(世話役)
-
六〜七段目:嫁入り道具や御所車など
このように、段を先ほどごとに「位置の違い」を表す構成となっていて、当時の宮中社会のあり方が反映されています。
静かな段飾りに優しいことで、自然と礼儀作法や人との関係性を学ぶように──という「しつけ」や「教養」の意味も含まれていたとされています。
■飾ることで、子どもに伝えたかったこと
段飾りはそのまま「人形の並び」ではありません。飾る順番には意味があり、それを家族で確認しながら準備を進めていく過程には、自然としきたりや礼儀を学ぶ要素がありました。
かつて、「三人官の真ん中は共婚者」「五人囃子の順番は音の高い楽器から」など。
子どもたちは、親や祖父母に学びながら人形を飾りながら、目に見えない「家の文化」を認めていたのだ。
■暮らしに寄り添って変化する仕組み
段飾りは、元々は武家や裕福な町の人あいだで楽しまれていたもの。
当時の江戸では、ひな祭りが華やかに展示され、人形職人たちの技が競い合うようになります。
その中で、お雛様をかなりきれいに、豪華に飾りたいという気持ちから、段を積み上げて高さを出すという「暮らしの工夫」も生まれました。
段階飾りは、実用性と美意識の両面から、広く一般の方にも受け入れられていきます。
■現代につながる、ひな壇の美しさ
今では、七段飾りだけでなく、三段や一段の「親王飾り」など、暮らしに合わせたさまざまなスタイルが親しまれております。ただし、段を重ねて
人形を飾るという文化は、長い時間をかけて日本人が育んできた、かけがえのない美意識の現れです。
「きちんと飾る」「意味を知って並べる」その
ひとつひとつの手仕事に、子どもを考える優しい気持ちが込められているからこそ、段飾りは時代を超えて受け継がれているのでしょう。
■現代の住まいに合わせた変化も
かつては七段飾りが主流だったもありましたが、最近では住宅事情や保管のしやすさを考慮して、三段や親王飾り(一段)など、コンパクトな飾り方も増えています。
「家族の恩恵」 「お子様の成長」「
幸せな人生」を願って、一歩ずつ丁寧に飾るひととき──それは、
春を迎える日本ならでは、やさしい祈りの時間です。