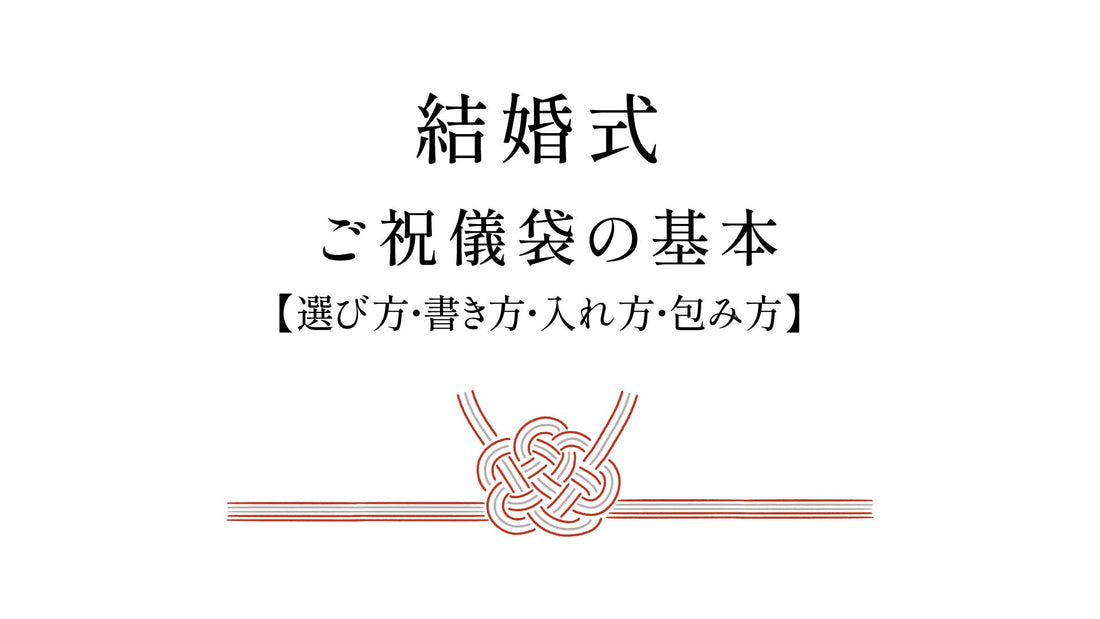結婚式に招かれたときに用意する「ご祝儀」。
気持ちを込めて贈るものだからこそ、マナーや心遣いも大切にしたいものです。この記事では、ご祝儀袋の選び方から、お札の入れ方、名前の書き方、包み方まで、ご祝儀袋の基本を丁寧にご紹介します。
【ご祝儀袋の選び方】
ご祝儀袋は、お祝いの気持ちを表す大切なもの。
金額や関係性に応じて、適したものを選びましょう。
◆ 水引の色と結び方に注目
ご祝儀袋には「水引」と呼ばれる飾り紐がついています。
結婚式には【紅白】または【金銀】の水引を選びましょう。結び方は「結び切り」や「あわじ結び」が基本です。どちらも「一度きりのお祝い」という意味があり、結婚のお祝いにふさわしいとされています。

◆ 金額に合ったデザインを
包む金額に対して、袋の格式が高すぎても安すぎても、少しちぐはぐな印象になってしまいます。
目安としては:
-
1万円程度…シンプルなデザインのもの
-
3万円程度…やや華やかなもの(刺繍や金箔が使われているものなど)
-
5万円以上…格式の高い、豪華なもの(箱入りタイプや飾りの多いもの)
◆ 贈る相手との関係も大切に
友人へのお祝いならカジュアルなデザインでもOKですが、上司や親族への場合は落ち着いた色合いや格式を意識すると安心です。
【ご祝儀袋の書き方】
ご祝儀袋の表書き(表面に書く文字)にもマナーがあります。
◆ 表書きの上段:「寿」や「御祝」
結婚式には「寿」や「御結婚御祝」、「御祝」などが一般的。
迷ったら「寿」と書くのが無難です。毛筆や筆ペンで、濃く丁寧に書きましょう。
◆ 表書きの下段:フルネームで
贈り主の名前は、水引の下にフルネームで記載します。
夫婦で贈る場合は、中央に夫の名前、左下に妻の名前を添える形が基本。連名の場合は、立場や年齢の順に右から並べます。送り主が多数の場合は、〇〇一同など関係性を表す送り書きにするか、
代表者の名前を一名書き、その左側に「外一同」と記し、全員の氏名を書いた紙を中に入れます。

【内袋の書き方】
中袋の表には「金額」、裏には、住所と名前を記入します。
◆ 金額の記入
中袋に金額を書く欄があれば、「金 参萬円」などと旧字体を使って記入します。
数字の書き方は以下を参考に:
-
一 → 壱
-
二 → 弐
-
三 → 参
-
万 → 萬
-
円 → 圓
例:「金 参萬円」となります。
【ご祝儀の入れ方】
中袋(中包み)にはお札を入れますが、細かなマナーがあります。
◆ お札は「新札」で用意
結婚のお祝いには、折り目のない新札を使うのがマナーです。事前に銀行などで用意しておきましょう。
◆ お札の向きに注意
ポイントは紙幣の向きは中袋(中包み)を開いたときに「肖像画」が見えること。
中袋にお札を入れる際は、お札の肖像(顔)が中袋の表側に向くように、かつ上にくるように入れます。封をする場合は、糊付けよりも軽く折り返す程度で構いません。
◆ 内袋がない場合
内袋がない場合は半紙、またはコピー用紙等を利用します。
<折り方>

◆ 包むタイミング
ご祝儀袋は前日に準備しておき、当日は持ち運びに便利な「ふくさ(袱紗)」に包んで持参します。会場で受付をするときに、袱紗からご祝儀袋を取り出して丁寧に渡しましょう。
そのままバッグに入れると袋の端が折れたり水引や熨斗が崩れたりすることもあるので、できれば使いたいもの。なければきれいなハンカチなどでも代用できます。
さいごに
結婚式は、ふたりにとってかけがえのない大切な日。そんな日に贈るご祝儀には、気持ちがこもっていることが何より大切です。マナーに気をつけながらも、温かな心を込めて贈れば、きっと喜んでもらえるはずです。
どうぞ素敵なお祝いのひとときをお過ごしくださいね。