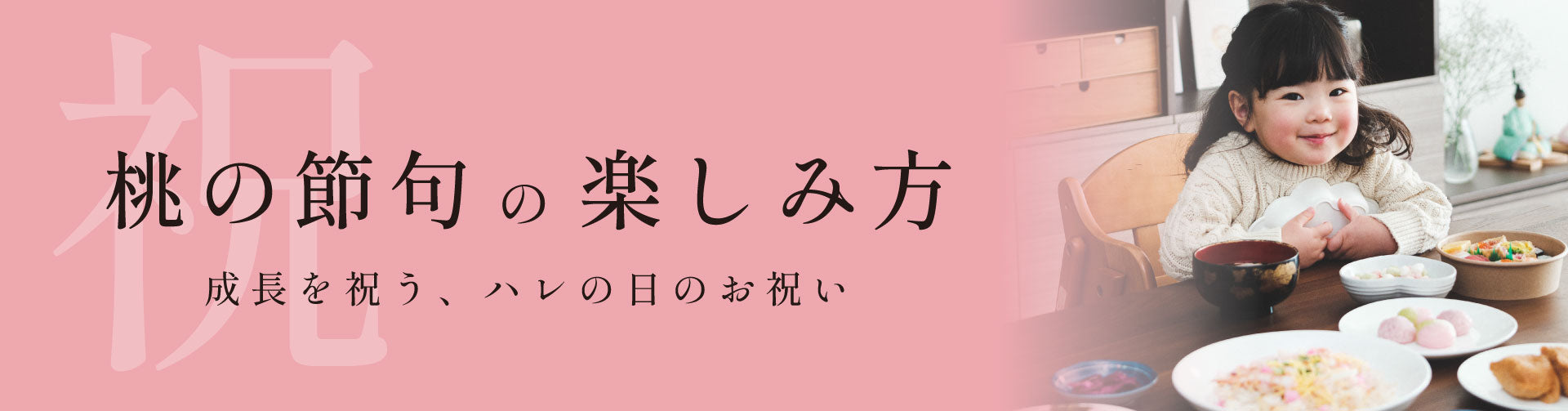【桃の節句】
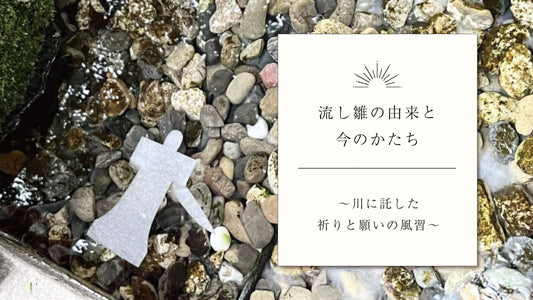
流し雛の由来と今のかたち 〜川に託した、祈りと願いの風習〜
桃の節句にまつわる風習のひとつに、「流し雛(ながしびな)」と呼ばれる伝統行事があります。流し雛は、現代のひな祭りの起源ともいわれる、大切な風習。そのはじまりと、今に伝わる姿をたどってみましょう。
流し雛の由来と今のかたち 〜川に託した、祈りと願いの風習〜
桃の節句にまつわる風習のひとつに、「流し雛(ながしびな)」と呼ばれる伝統行事があります。流し雛は、現代のひな祭りの起源ともいわれる、大切な風習。そのはじまりと、今に伝わる姿をたどってみましょう。
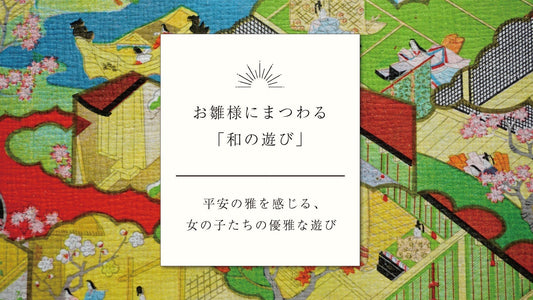
お雛様にまつわる「和の遊び」〜平安の雅を感じる、女の子たちの優雅な遊び〜
雛人形のルーツとされる「ひいな遊び」が行われていた平安時代には、身分の高い子どもたちが日々の中で楽しむ、繊細で美しい「和の遊び」が数多くありました。
お雛様にまつわる「和の遊び」〜平安の雅を感じる、女の子たちの優雅な遊び〜
雛人形のルーツとされる「ひいな遊び」が行われていた平安時代には、身分の高い子どもたちが日々の中で楽しむ、繊細で美しい「和の遊び」が数多くありました。

平安時代の「ひいな遊び」とは?
ひなまつりのルーツをたどっていくと、平安時代に行われていた「ひいな遊び(ひいなあそび)」という、可愛らしい遊びにたどり着きます。この「ひいな」は、現在の「雛(ひな)」と同じ意味をもち、「小さくて、かわいらしいもの」を表す言葉でした。
平安時代の「ひいな遊び」とは?
ひなまつりのルーツをたどっていくと、平安時代に行われていた「ひいな遊び(ひいなあそび)」という、可愛らしい遊びにたどり着きます。この「ひいな」は、現在の「雛(ひな)」と同じ意味をもち、「小さくて、かわいらしいもの」を表す言葉でした。

なぜ3月3日にお雛様を飾るの?
春のはじまりを感じる3月。この時期に行われる「桃の節句」は、女の子の健やかな成長を願う、大切な年中行事です。では、なぜこの日、「お雛様」を飾ってお祝いするようになったのでしょうか?
なぜ3月3日にお雛様を飾るの?
春のはじまりを感じる3月。この時期に行われる「桃の節句」は、女の子の健やかな成長を願う、大切な年中行事です。では、なぜこの日、「お雛様」を飾ってお祝いするようになったのでしょうか?
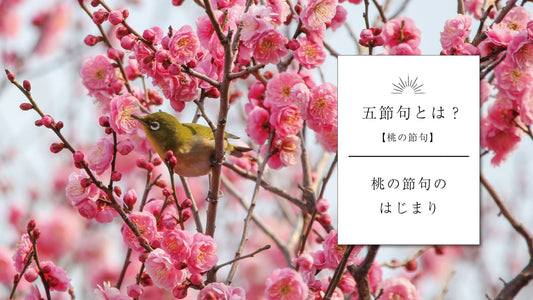
五節句とは? 桃の節句のはじまり
私たちの暮らしの中には、季節ごとに訪れる「節句(せっく)」と呼ばれる伝統行事があります。そのひとつが、女の子の健やかな成長を願って行われる「桃の節句」です。
五節句とは? 桃の節句のはじまり
私たちの暮らしの中には、季節ごとに訪れる「節句(せっく)」と呼ばれる伝統行事があります。そのひとつが、女の子の健やかな成長を願って行われる「桃の節句」です。

お雛様は誰が贈るの?
雛人形は母親の実家(祖父母)から贈るのが一般的です。