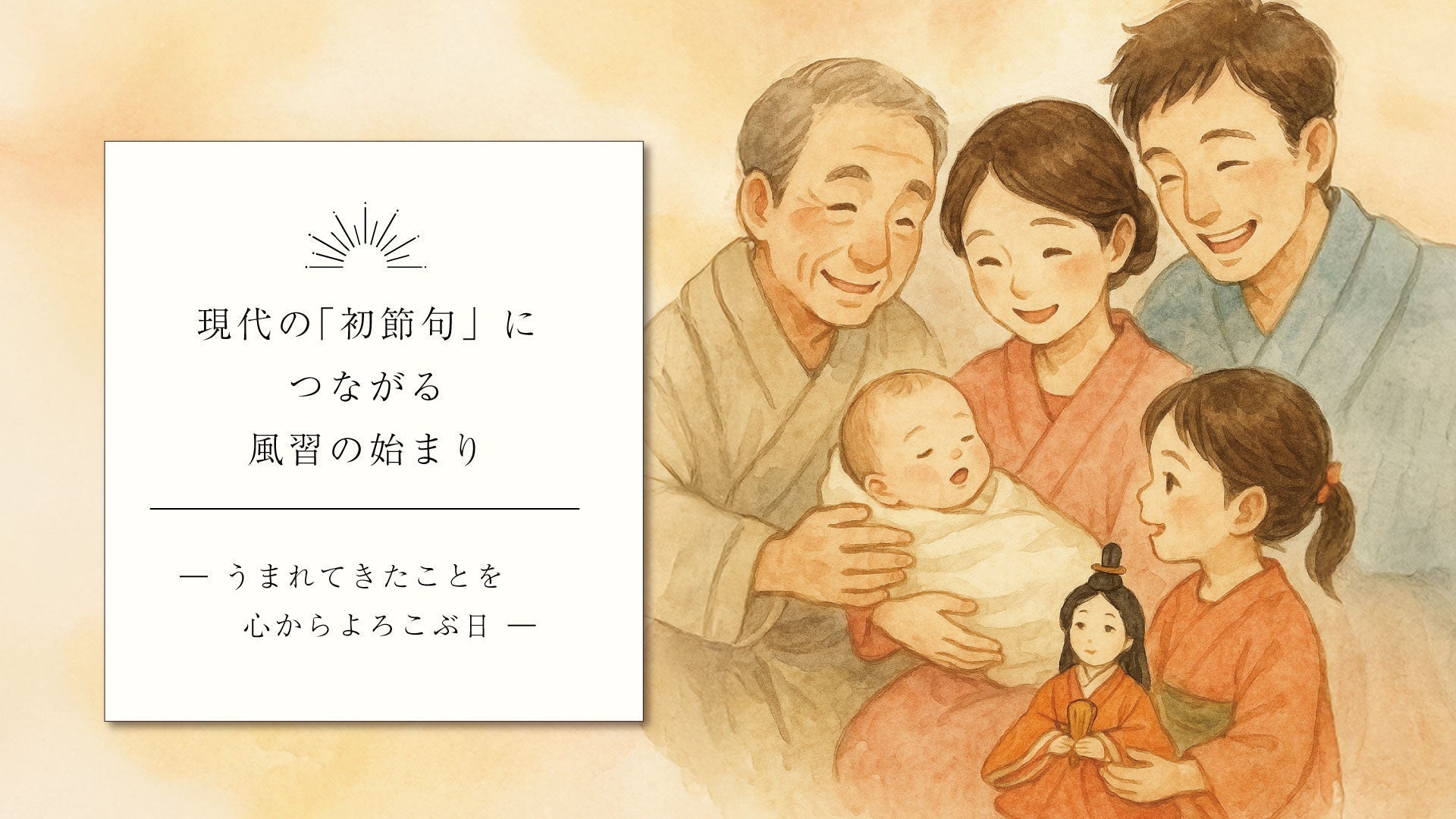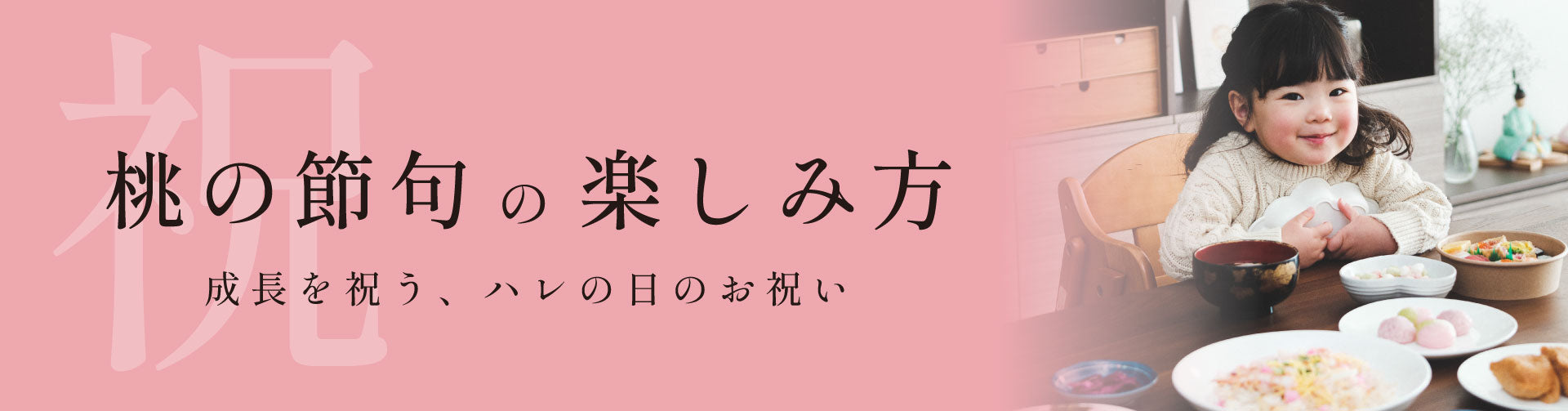私たちの暮らしの中には、季節ごとに訪れる「節句(せっく)」と呼ばれる伝統行事があります。
そのひとつが、女の子の健やかな成長を願って行われる「桃の節句」です。
■ 「節句」は、季節の変わり目を大切にする風習

「節句」とは、季節の節目のことをいいます。
昔の人々は、季節の変わり目には邪気(じゃき)が入りやすいと考え、身を清めたり、災いを避けるための儀式を行っていました。
たとえば、身を水で清める「禊(みそぎ)」や、病や災厄を祓うための「祓い(はらい)」といった風習がそうです。
こうした風習は、日本古来の信仰と共に、中国から伝わった宮中行事の影響も受けながら、長い年月をかけて形づくられていきました。
■ 日本の「禊祓」と中国の「上巳節句」が出会う
桃の節句の起源には、中国から伝わった「上巳(じょうし)の節句」が深く関わっています。
この行事は、3月のはじめに川で身を清め、宴をひらいて災いを遠ざけるというもので、自然の力を借りて邪気を祓うという考え方に基づいていました。
この風習が日本に伝わると、日本古来の「禊祓(みそぎはらい)」や、「人形(ひとがた)」と呼ばれる紙の人形に穢れ(けがれ)をうつして川に流す風習と結びつきます。
平安時代になると、祈祷師(きとうし)を招いて人形に厄を移し、供物(くもつ)を添えて川に流すという行事が、宮中でも行われるようになりました。
この流れが、のちに「流し雛(ながしびな)」として受け継がれ、現在の雛祭りの原型になっていきます。

■ 五節句のひとつとしての「桃の節句」

日本では、季節の節目に行う行事のうち、特に重要とされた5つの節句が「五節句(ごせっく)」と呼ばれます。
-
1月7日:人日の節句(七草の節句)
-
3月3日:上巳の節句(桃の節句)
-
5月5日:端午の節句
-
7月7日:七夕の節句
-
9月9日:重陽の節句
このなかで「桃の節句」は、春の訪れとともに、命の芽吹きや清らかさを象徴する行事です。
古くは宮中での儀式として、人生のはじまりに願いを込める行事として庶民の間でも広まり、現在では、女の子の健やかな成長を願う家族の行事として親しまれるようになりました。五節句の中でも特に「家族の行事」として定着してきたのが、「桃の節句」をはじめ「端午の節句」のお節句行事になります。
■ 家族の願いを込める、やさしい節目
男の子の「端午の節句」と並び、「桃の節句」は、子どもの成長を願う大切な節目として、家庭に受け継がれてきました。
季節の巡りを感じながら、家族で願いを込める――。
そのやさしい風習は、今も変わらず、私たちの暮らしにそっと寄り添っています。